![]()
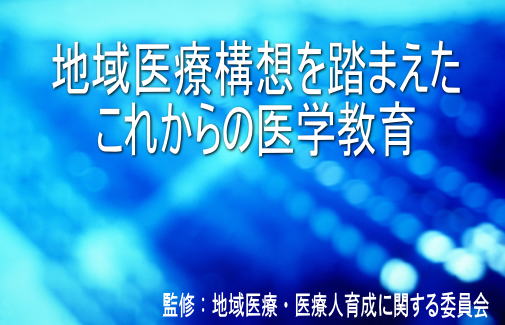 |
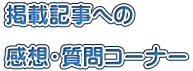 |
| |
|
各大学の掲載記事について、ぜひご感想・ご質問等をお寄せください。
メールに①ご感想・ご質問等、②ご所属・お名前、③ご意見・ご感想およびご所属名の掲載の可否を
明記の上(お名前は掲載いたしません)、国立大学医学部長会議事務局(info*chnmsj.jp ←*を@に変えて
ください。)までお送りください。
| 第32回 福井大学の記載事項(R6.5.23記載)への感想・質問 |
|---|
| 入学後の「新入生オリエンテーション」はユニークですね。先生方の思い入れが強く伝わります。また、他大学との交流も参考になるところです。 1)「地域医療早期体験プログラム」、「地域医療学」、「社会と医学・医療」について、それぞれ必修科目だと思いますが、体験や実習は、各々どのくらいの時間行っているでしょうか。 時間数がどれくらいかが話題となりますので、お聞きするところです。 2)様々な学外実習での、交通費・宿泊費などの費用については、どのように運営されているのでしょうか。 (鹿児島大学) |
| 【質問1.】 「地域医療早期体験プログラム」、「地域医療学」、「社会と医学・医療」について、それぞれ必修科目だと思いますが、体験や実習は、各々どのくらいの時間行っているでしょうか。 時間数がどれくらいかが話題となりますので、お聞きするところです。 【回答1.】 ●「地域医療早期体験プログラム」は、医学科1年次生後期 必修科目で、次の実習を6日間で設定しています。 ・仁愛大学での合同調理実習 ・・・ 2グループに分かれ日を変えて実施 ・高浜町の地域医療現地見学 ・・・ 2グループに分かれ日を変えて実施 ●「社会と医学・医療Ⅰ」は、医学科3年次生後期 必修科目で、介護や福祉に関連する施設における実習を2日間で設定しています。 ●「地域医療学実習」は、医学科3年次生前期 選択科目で、本学総合診療部を始め地域中核病院や診療所における実習を5日間で設定しています。※地域医療学(講義)は医学科2年次必修科目 ●「社会と医学・医療Ⅱ」は、医学科4年次生前期 必修科目で、医師や公衆衛生従事者が勤務する県内の施設における実習を9日間で設定しています。 【質問2.】 様々な学外実習での、交通費・宿泊費などの費用については、どのように運営されているのでしょうか。 【回答2.】 ●「地域医療早期体験プログラム」については、バス代を厚生労働省「総合的な診療能力を持つ医師養成の推進事業」補助金で支出しています。なお、仁愛大学での合同調理実習については、食材とガウンも支出しています。 ●「地域医療学実習」については、各自で移動(宿泊なし)となり大学負担はしていません。 ●「社会と医学・医療Ⅰ」については、班ごとに実習先へ直行(宿泊なし)となり大学負担はしていません。 ●「社会と医学・医療Ⅱ」 については、1人3,500円以内は自己負担とし、それを超える分は大学で補助しています。 ●その他、「地域包括ケア実習」(※実施診療参加型臨床実習Ⅰの一部として実施)での実習として以下を実施し、厚生労働省「総合的な診療能力を持つ医師養成の推進事業」補助金でバス代を支出しています。 (1)医学科5年次生が12機関×2日程のグループに分かれ、厚労省補助金事業の協力医療機関の病院、診療所等を見学し、現場の様子を体験 (2)福井医療大学での合同実習 ・・・ 医学科5年次生が2グループに分かれ日を変えて実施 |
| 入学後のオリエンテーション時の取り組みなどを通じて、6年間の継続的な地域医療教育、多職種協働教育を実践されていること、素晴らしいと感じました。 4年時の健康福祉センター(保健所)での見学実習も重要と感じました。 3)この実習期間はどのくらいでしょうか。 4)数日間通うことで地域医療での、その重要性、多様な業務を理解させるようなカリキュラムなのでしょうか。ご教示いただけますと幸いです。 (新潟大学) |
| 【質問3.】 この実習期間はどのくらいでしょうか。 【回答3.】 回答1と同じとなります。 【質問4.】 数日間通うことで地域医療での、その重要性、多様な業務を理解させるようなカリキュラムなのでしょうか。 【回答4.】 本学医学部の特色あるカリキュラムとして「地域医療」を設定しています。本学医学部のミッション「強みや特色などの役割」において、「今後のさらなる高齢化等の社会状況の変化、ER 型救急への取組実績、また原子力関連施設が数多く存在する福井県の地域事情等を踏まえ、救急医療に強い総合医、緊急被ばく医療人材の養成など、地域社会のニーズに対応した優れた指導的医療人を育成するシステムを構築する。」と定義されています。 地域とくに福井県の医療事情を踏まえた地域医療を学ぶ科目を、学年を超えて学ぶことができるようにカリキュラムの中に配置しています。(アウトカム3 医療人としての地域性・国際性、コンピテンシー(7)、(8)) |
| 第31回 筑波大学の記載事項(R6.4.5記載)への感想・質問 |
|---|
| 1)各都道府県の二次医療圏毎の必要医師数の計算が必要であり、今後の地域枠の定員数や、全体の定員数試算の根拠になっていくと思われます。筑波大学及び茨城県では、この必要医師数について、どのような方策で臨むのでしょうか。 2)茨城県内の研修医数は増加していると思いますが、その後の診療科の偏在はあると思います。診療科毎のバランスを考慮する中で、生物学的、精神的、社会的ニーズが増すと考えられる総合診療医の育成に関し、どのような方針で臨み、どのような教育(専門医でありながら全人的に診る医師を育成するのか、総合診療医そのものを増やすのかなど)を今後展開すべきとお考えでしょうか。 3)政治の動きで単に医師の増加を考えるのではなく、将来を見据えた大学と自治体の方針が一致することが望ましいです。そのための工夫や、今後の期待があれば教えてください。 (鹿児島大学) |
| 【質問1.】 各都道府県の二次医療圏毎の必要医師数の計算が必要であり、今後の地域枠の定員数や、全体の定員数試算の根拠になっていくと思われます。筑波大学及び茨城県では、この必要医師数について、どのような方策で臨むのでしょうか。 【回答1.】 茨城県は医師少数県であり、今のところ専攻医のシーリングがかかっている領域もないため、必要医師数に関する議論の優先順位はそれほど高くありません。その一方で、茨城県では現在11大学に70名(うち筑波大学は36名)の地域枠が設定されており、卒業後の義務を果たすことができるキャパシティの確保が問題になっており、その観点から、地域枠の定員数の見直す必要性について議論が始まっています。 【質問2.】 茨城県内の研修医数は増加していると思いますが、その後の診療科の偏在はあると思います。診療科毎のバランスを考慮する中で、生物学的、精神的、社会的ニーズが増すと考えられる総合診療医の育成に関し、どのような方針で臨み、どのような教育(専門医でありながら全人的に診る医師を育成するのか、総合診療医そのものを増やすのかなど)を今後展開すべきとお考えでしょうか。 【回答2.】 ご指摘のように、地域医療(医師不足地域を含む)において専門性を発揮でき、幅広い領域をカバーできる総合診療医は、医師の地域偏在、診療科偏在を改善するうえで非常に有用な存在であると考えています。その養成には、卒前教育、臨床研修、専門研修、生涯学習すべてのフェーズにおける教育研修システムの充実が求められると思います。総合診療専門医を増やすことはもちろん重要ですが、ご指摘のように専門医でありながら全人的にみる医師の養成も極めて重要であり、総合的な診療に関するリカレント教育やキャリア支援などに取り組んでいきたいと考えています。 【質問3.】 政治の動きで単に医師の増加を考えるのではなく、将来を見据えた大学と自治体の方針が一致することが望ましいです。そのための工夫や、今後の期待があれば教えてください。 【回答3.】 ご指摘の通りだと思います。地域医療対策協議会、地域医療構想調整会議などにおいて、大学と自治体が議論を深めるとともに、二次医療圏、市町村単位での議論にも大学が積極的にコミットして、一致して医師確保計画の推進に取り組んでいきたいと考えております。実際には、各ステークホルダーの思惑が一致しないことも多く、コンセンサスを得るのは難しい部分もありますが、将来の地域医療を見据えながら、議論を重ねていきたいと考えています。 |
| 第30回 鳥取大学の記載事項(R6.4.2記載)への感想・質問 |
|---|
| 1)必要医師数の計算は、単に医療機関からの希望を表現しているのでしょうか。それとも、人口動態や診療科の状況などを勘案し、計算しているものなのでしょうか。 鳥取県では、2005年から2023年までをおよそ5年ごとに分けて計算した場合の、人口10万人当たりの1年目の研修医数は着実に増加していると認識しています(日本専門医機構データ)。 鳥取県内での臨床研修者数に占める地域枠OBの割合が増加していることもそれを裏付けていると思います。一方で地域枠医学生を県内出身者のみに限定すると、学力の維持が難しくなると推察されます。県外の地域枠医学生は離脱し易いと言うデータもあります。 2-1)鳥取県出身者の場合の学力維持の工夫は必要でしょうか。必要ならその対策を御教授ください。 2-2)兵庫県枠、島根県枠を設定していることの利点と、問題点はどのようなものでしょうか。 (鹿児島大学) |
| 【質問1.】 必要医師数の計算は、単に医療機関からの希望を表現しているのでしょうか。それとも、人口動態や診療科の状況などを勘案し、計算しているものなのでしょうか。 【回答1.】 鳥取県内の医師数に関する調査につきご質問ありがとうございます。以下に回答させていただきます。 ・医師数に関しては、県内43病院に対し、各診療科と病院全体の現員数と必要数の調査を行っています。 ・現員数は、調査対象年1月1日現在の医師数で、初期臨床研修医を除いています。なお、非常勤医師については、常勤換算しています。 ・必要数は、現行の診療体制を基本とした上で、それぞれの病院が対象年4月1日に必要としている医師数です。 ・必要数と現員数の差(不足数)については、各医療機関に採用計画とその理由(例:常勤医の負担軽減、高齢医師の退職等)を別様式に記入し提出してもらっております。(一部採用計画の記載のないものがあります) ・ご質問のように、人口動態や診療科の状況を勘案したものではなく、各医療機関の希望と現実的な採用計画に基づいた数字となります。 (回答者 鳥取県地域医療支援センター) 【質問2-1.】鳥取県出身者の場合の学力維持の工夫は必要でしょうか。必要ならその対策を御教授ください。 【回答2-1.】 入学者(鳥取県枠)の成績状況については、2021年(令和2年度)より地域枠を併願でなく別枠入試とした時点から、一般入試枠より成績が悪くなることが懸念されていました。R6年度入試の実績では、鳥取県の特別養成枠、臨時養成枠などは、最低点は少し低いものの平均点はさほど差がありませんでした。いちばん懸念されるのは、島根県枠の応募者実数が少なくなり成績低下が目立っていることです。入学後の学力維持は、学生全体を10班ほどのグループに分けて、チューター教官を2名ずつ付けて、学力不良者、メンタルを抱える学生に対応するようにしています。また並行して、地域枠学生には地域医療学講座が正規カリキュラム外のプロジェクトを提案し、応答の鈍い学生にはリマインドや面談をするようにしています。とくに鳥取県出身者の学力低下が著しいとは感じませんが、低学年での成績不良者、留年者は、M4でのCBT点数も低く、M5臨床統合試験の点数も悪く、国家試験不合格のハイリスクとなっていきます。とくに、留年者、CBT不合格者には、鳥取県出身か否かを問わず、重点的にチューターがサポートするようにしています。 (回答者 地域医療学講座) 【質問2-2.】兵庫県枠、島根県枠を設定していることの利点と、問題点はどのようなものでしょうか。 【回答2-2.】 島根県枠は、臨床研修はR2年貸付者から島根県内限定ですが、医師3年目以降は鳥取大学医局に所属しつつ専門医取得も可能です。一定期間は島根県の指定病院で働くことが求められますが、もともと鳥取大学は島根県東部医療圏域をカバーしてきた歴史があり、安来、松江地区は米子からの通勤圏でもあり、島根県枠医師と鳥取大学医局の双方にとってメリットになっていると思います。ただし、卒後に島根大学所属で研修する場合、鳥取大学との連関は完全に切れてしまいます。また、鳥取大学医局から派遣のない島根県西部や隠岐島などには派遣が難しい場合があります。兵庫県枠は卒後すぐに兵庫県内病院に勤務が義務付けられており、鳥取大学にとって医学部定員数確保以外にほとんどメリットはありません。兵庫県内大学の地域枠と比べて、初期臨床研修病院での臨床実習が認められないなど、学生にとって不利な点はあるかと思います。 (回答者 地域医療学講座) |
| 第29回 金沢大学の記載事項(R6.2.19記載)への感想・質問 |
|---|
| 1)診療参加型臨床実習として、学内で行われている具体的な例としてどのようなものがあるでしょうか。 2)学外施設を十分に活用した臨床実習を行っているようですが、遠い地域の医療機関の指導医へのFDはどのように行っているのでしょうか。 3)学外施設に、1人/1か所を派遣しているようですが、良い点と悪い点を教えてください。 4)総合診療教育は、特に能登地方で必要なようなプライマリ・ケア領域は、高度先進医療が大きな目的の大学病院では難しいと考えます。どのように、石川県で教えていくことをお考えでしょうか。 (鹿児島大学) |
| 【質問1.】 診療参加型臨床実習として、学内で行われている具体的な例としてどのようなものがあるでしょうか。 【回答1.】 学内外を問わず、実習診療科の診療チームの一員として診療に参加させて頂くよう各科に依頼しております。学内では病棟中心となることが多く、主治医の一人として担当患者を毎日診察し、チーム回診時のプレゼンとディスカッション、フィードバック、およびカルテ記載を必須としています。また、CC-EPOCを利用して各症候に関する臨床推論の記載(800字以上)とフィードバック、基本的臨床手技の評価、EPAの評価、資質・能力の評価、各診療科1回のmini-CEXを依頼しています。 【質問2.】 学外施設を十分に活用した臨床実習を行っているようですが、遠い地域の医療機関の指導医へのFDはどのように行っているのでしょうか。 【回答2.】 教育提携医療機関の指導医には成人学修理論、Workplace-based Evaluationに関する内容等について年1回講演会を開催し、臨床実習インストラクター、シニアインストラクター等の称号を付与して、指導にあたっていただいております。また毎月1回連絡協議会をオンラインで開催し、情報共有を図っております。 【質問3.】 学外施設に、1人/1か所を派遣しているようですが、良い点と悪い点を教えてください。 【回答3.】 原則1施設1名を派遣しているのは、「総合診療科・地域医療」実習です。金沢大学からの学生は同時期に一人しかいないため、学生だけが固まって周囲に対して壁を作ることができないことから、所属するチームの医師はもちろん、他科の医師や多職種の職員と自然に交流することになり、地域医療機関が果たしている役割を肌で学んでもらえることを期待しています。なお、実習先の中には複数の大学から実習生を受け入れている医療機関がいくつかあり、そのような実習先では他大学の学生と交流する機会が生まれ、互いに刺激を受けたり、自大学を(長所・短所を含めて)客観的に観ることができる効果もあるようで、特に希望者は多くなっています。 一方、一人であることの不安を吐露する学生が一部にいました。滞在費用はかかりませんが、往復交通費は学生負担です。 【質問4.】 総合診療教育は、特に能登地方で必要なようなプライマリ・ケア領域は、高度先進医療が大きな目的の大学病院では難しいと考えます。どのように、石川県で教えていくことをお考えでしょうか。 【回答4.】 「総合診療科・地域医療」臨床実習では、医師少数区域あるいは過疎地域に指定されている能登北部や能登中部、あるいは新潟県上越医療圏を含む地域密着型医療機関に原則として1施設1名を派遣しています。この実習では、全学生が4週間にわたり、プライマリ・ケアや在宅診療、回復期・慢性期医療等を学びますが、地域滞在中に地域アセスメントのレポートを作成し、また実習中に担当した患者さんに関して実習最終日に大学に戻って行動科学・社会科学に焦点を当てた事例発表とディスカッションを行わせています。その他、学生は各医療機関で1回ずつ症例発表を行いますが、そのうち1例について、全実習機関をつないだオンライン教育カンファレンスを開催しています。 なお、地域医療に興味がある学生には、11週連続のインターンシップが選択できるプログラム(Extended Community Elective, EXCEL)を用意しています。また、看護学専攻の保健師コースとの多職種連携授業として地域アセスメント演習を行い、「地域を診る」視点を養う試みも数年にわたり行っています。 |
| 第28回 宮崎大学の記載事項(R6.1.29記載)への感想・質問 |
|---|
| 5-6年次の長期滞在型地域医療実習は、初診から看取りまで、チームの一員として12週間、診療に従事する素晴らしい取り組みであると思います。 1)LICを展開している都農町国民健康保険病院の病床数、常勤医数をご教示ください。 2)都農町国民健康保険病院では、長期・短期実習の学生が同時に実習することもあるのでしょうか? 3)4週間の「地域包括ケア実習」では、どのような医学的スキルの習得が目標にされるのでしょうか? 4)医師派遣調整は大学が行うのか、地域医療支援センターが行うのか、大学と地域医療支援センターの関係についてもお教えください。 (新潟大学) |
| 【質問1.】 LICを展開している都農町国民健康保険病院の病床数、常勤医数をご教示ください。 【回答1.】 都農町国民健康保険病院は、一般病床61床、感染症病床4床 計65床です。 常勤医は9名で、内訳は、総合診療医6名、整形外科医1名、小児科1名、眼科1名となっています。 【質問2.】 都農町国民健康保険病院では、長期・短期実習の学生が同時に実習することもあるのでしょうか? 【回答2.】 長期実習(3か月)の学生は年3名となっています。 この間、同時に短期実習(4週)の学生が同時に実習することもあります。 さらに、宮崎大学の初期研修医が地域医療研修(1か月)として同時に研修することがあります(枠として月1名)。 結果、最大で2名の学生、1名の初期研修医の計3名が同時に研修・実習することがあります。 【質問3.】 4週間の「地域包括ケア実習」では、どのような医学的スキルの習得が目標にされるのでしょうか? 【回答3.】 個別の医学的スキルの設定はしておりませんが、以下の表にしてある学習目標を設定して現地に送り出しております。 また臨床実習全体の共通した評価票(9つのコンピテンシーとそのルーブリック)で現地指導医、多職種スタッフ、講座教員で評価を実施しております。 ・地域医療の定義を言える ・「研修医0年目」という意識を体に染み込ませる ・一緒にこの1ヶ月を闘う仲間のことを知る ・地域包括ケアシステムの植木鉢モデルを理解できる ・自分が赴任する地域のこと、医療機関、指導医のことを少し理解できる ・きちんと大きな声で挨拶ができる ・報告、連絡、相談ができる ・実習中は毎日メモをとり、夕方・夜に振り返りシートを記入、アップできる ・実際にどんなことまでやるのかをイメージできる ・地域及びこの実習を楽しむコツを先輩たちの発表から得る 【質問4.】 医師派遣調整は大学が行うのか、地域医療支援センターが行うのか、大学と地域医療支援センターの関係についてもお教えください。 【回答4.】 現在、宮崎県及び宮崎大学に医師派遣調整を統括する機能はありません。 宮崎大学では、以前より各医局が、各医療機関の要請に基づき派遣しています。 キャリア形成プログラムが適用されている地域枠生についても、各プログラムを所管する医局が医師配置を行っている状況です。 なお、宮崎県は、宮崎大学内に地域医療支援センター(地域医療支援機構大学分室)を設置し、キャリア形成プログラムを運用しています。 地域医療支援機構大学分室の室長は、医学部医療人育成推進センター教授(大学病院卒後臨床研修センター長兼務)が担っています。 今後、医師派遣調整を宮崎大学、宮崎県としてどう取り扱うか検討することとしています。 |
| 第27回 鹿児島大学の記載事項(R5.12.22記載)への感想・質問 |
|---|
| 地域医療は「住民を取り巻いている、生活する領域、基本的社会で行われる医療」とのお考えに賛同します。 1)地域医療構想調整会議を20回開催したとの事ですが、県全体会議が20回でしょうか? それとも圏域別の会議を含めて20回でしょうか? 2)1年次?3年次に地域で初期医療実習を行う段階的教育と継続性が素晴らしいと感じましたが、この実習のマネジメントは医学部のどの部署が担当しているのでしょうか? 3)その実習は選択科目とのことですが、毎年どのくらいの学生が選択しているのでしょうか? 4)離島実習の際の交通費、宿泊費などはどの様な形で出ているのでしょうか? (学生負担? 医学部負担?) 5)産業別就業者数で医療・福祉が19.1%とのことです。この数字は国内でもかなり高いと思われますが、その理由を教えてください。 (新潟大学) |
| 【質問1.】 地域医療構想調整会議を20回開催したとの事ですが、県全体会議が20回でしょうか? それとも圏域別の会議を含めて20回でしょうか? 【回答1.】 県全体会議です。個別の域内の開催状況は確認できておりません。 【質問2.】 1年次?3年次に地域で初期医療実習を行う段階的教育と継続性が素晴らしいと感じましたが、この実習のマネジメントは医学部のどの部署が担当しているのでしょうか? 【回答2.】 医歯学総合研究科の、離島へき地医療人育成センターが管理運営しています。 【質問3.】 その実習は選択科目とのことですが、毎年どのくらいの学生が選択しているのでしょうか? 【回答3.】 地域枠医学生、各学年18-20名ですが、それは全員です。一般学生は、希望者として4-5名です。 【質問4.】 離島実習の際の交通費、宿泊費などはどの様な形で出ているのでしょうか? (学生負担? 医学部負担?) 【回答4.】 1、2、3年生の地域枠は、全額県の予算です。 6年生の全員の必修の「離島・地域医療実習」は、自己負担、離島へき地医療人育成センターの運営費、寄付金が1/3ずつです。 【質問5.】 産業別就業者数で医療・福祉が19.1%とのことです。この数字は国内でもかなり高いと思われますが、その理由を教えてください。 【回答5.】 一般に、地方ほど、医療・介護・福島関係の就業者が多いのが一般的です。これは鹿児島に限ったことではありません。 |
| 第26回 山形大学の記載事項(R5.11.13記載)への感想・質問 |
|---|
| 1)医学科4年次「総合医学演習:地域医療学」の病院見学に関する学生の声をお教えください。現在の半日をさらに延長してほしいなどの要望はあるでしょうか? 2)広域連携臨床実習は5年生対象でしょうか? 実習先は学生の選択によるものでしょうか? 3)広域連携臨床実習は、医療政策学講座がマネージし、3病院、3クールで計3カ月の診療科横断的実習、という理解でよろしいでしょうか? 4)広域連携臨床実習の具体的な内容についてお教えください。 5)実習後に学生から得られるフィードバックは、どのように実習先と共有されていますか? 6)地域枠卒業生の配置については県が中心になって決めているのでしょうか、それとも大学側が決めているのでしょうか? (新潟大学) |
| 【質問1.】 医学科4年次「総合医学演習:地域医療学」の病院見学に関する学生の声をお教えください。現在の半日をさらに延長してほしいなどの要望はあるでしょうか? 【回答1.】 病院見学については,好意的な声が多いと感じます。 普段行くことのない県内の僻地にある病院(今年度は小国町,最上町)で行われるため、実際の見学では,学生から現場の医療職員に多くの質問がありました。 病院見学自体は半日ですが、遠隔地の病院に伺うため、片道1~2時間程度かかり、実質一日の病院見学となっております。 よって、日程についての要望は特に出ておりません。 【質問2.】 広域連携臨床実習は5年生対象でしょうか? 実習先は学生の選択によるものでしょうか? 【回答2.】 5年生10月から6年生6月にかけての臨床実習期間の一部として実施します(回答3を参照)。実習先はある程度学生の希望を確認したうえで、事務で割り振りを行います。 【質問3.】 広域連携臨床実習は、医療政策学講座がマネージし、3病院、3クールで計3カ月の診療科横断的実習、という理解でよろしいでしょうか? 【回答3.】 医療政策学講座がマネージメントしているものではなく、医学部教務委員会で所掌している授業となります。5年生10月から6年生6月にかけて、1Phase4週間、8Phaseの臨床実習を行い、その期間の中の3Phaseを、広域連携病院において実習を行っています。現在,県内各地域の15病院に広域連携病院としてご協力いただいております。スケジュールの割り振りは事務が行います。 【質問4.】 広域連携臨床実習の具体的な内容についてお教えください。 【回答4.】 実習の内容については、本学附属病院での実習内容に準じて、それぞれの病院の実情にあわせて実習を計画していただいており、広域連携病院の裁量に任せております。 【質問5.】 実習後に学生から得られるフィードバックは、どのように実習先と共有されていますか? 【回答5.】 学生から得られる学修効果などの広域連携病院とのフィードバックは、現在仕組みが確立されておらず、今後の課題と考えております。 なお、年に1回5月をめどに、広域連携臨床実習運営会議を開催しており、広域連携病院と大学との情報共有などを行っております。 【質問6.】 地域枠卒業生の配置については県が中心になって決めているのでしょうか、それとも大学側が決めているのでしょうか? 【回答6.】 地域枠の制度が年度によって異なっており、すべての学生が該当するわけではありませんが、地域枠卒業生の配置については、入局者は県が大学の各医局との調整を行い、地域医療対策協議会での協議を経た上で、県が決めています。 |
| 第25回 弘前大学の記載事項(R5.10.30記載)への感想・質問 |
|---|
| 地域と共に創造する、という貴学の方針を反映する様々な取り組みをご紹介いただきありがとうございました。下記5点についてお教えください。 1)3年次の社会医学実習はとても魅力的に感じます。これは全学生必修、地域枠学生必修、希望制、いずれでしょうか?健診会場の数や関わる学生の人数、役割などについてご教示いただけますでしょうか? 2)トライアルとして開始した5年次生の遠隔シミュレーション教育では、どのようなことをするのでしょうか? 3)6年次のクリニカルクラークシップ全体の期間をご教示ください。また、僻地医療実習以外のクリニカルクラークシップは、どのような実習(学内あるいは学外)を構築されておられるでしょうか? 4)医学生と看護学生による病棟実習は、どのような内容でしょうか? 5)正課の授業の履修により「防災士」の受験資格が得られることはとても魅力的なことと思います。差し支えなければ実際に受験した人数、試験に合格して防災士の資格を得られた人数などをご教示いただけますでしょうか? (新潟大学) |
| 【質問1.】 3年次の社会医学実習はとても魅力的に感じます。これは全学生必修、地域枠学生必修、希望制、いずれでしょうか?健診会場の数や関わる学生の人数、役割などについてご教示いただけますでしょうか? 【回答1.】 3年次全学生必修の社会医学実習の一部として、岩木健康増進プロジェクト(大規模住民合同健診)への参加を行っています。検診は1会場で10日間行われ、学生は5グループに分かれての参加となります。実際には、各ブースでの検診業務の補助を行います。具体的には、担当者(測定者など)とチームを組んで、誘導、体位補助、危険防止、説明などを行っています。 岩木健康増進プロジェクトの概要は、大学ホームページ https://coi.hirosaki-u.ac.jp/iwaki_pj/ をご覧ください。写真も掲載されており、大規模住民合同健診の様子が把握できます。 【質問2.】 トライアルとして開始した5年次生の遠隔シミュレーション教育では、どのようなことをするのでしょうか? 【回答2.】 秋田大学と連携し、秋田大学シミュレーションセンターと弘前大学とをテレビ会議システムを用いて接続し、弘前大学の5年次学生を対象に、架空症例提示および高機能シミュレーターを用いてシミュレーションを実施するものです。秋田大学シミュレーション室を救急外来や病棟に見立て、急変した症例(シミュレーター)について、弘前大学の5年次学生が、病歴やテレビ会議システム画面に表示されるモニター値から病態を評価し、診断推論を学ぶセッションです。1回の2時間セッションで2症例を取り扱いました。学生からは好評で、今後、教育プログラムとしての確立を検討しています。 【質問3.】 6年次のクリニカルクラークシップ全体の期間をご教示ください。また、僻地医療実習以外のクリニカルクラークシップは、どのような実習(学内あるいは学外)を構築されておられるでしょうか? 【回答3.】 5年次クリニカル・クラークシップ(臨床実習Ⅰ:44週)で全診療科をローテーションした後の6年次クリニカル・クラークシップ(臨床実習Ⅱ)は、28週で、4週間単位(7クール)の選択制ローテーションとなります。2023年度の実施期間は、3月20日~11月10日でした(7月31日~9月1日は実施せず)。7クールのうち、1クールはへき地医療機関(13医療施設)で実習を行います。残りの6クールについては、学内診療科と学外連携協力病院(20学外教育病院)の診療科の中から、学生が6診療科を選択し実習を行っています。このため、6年次学生は、かなりの期間(個々の学生で異なりますが、概ね半分程度)を、学外の医療機関で臨床実習を行っています。 【質問4.】 医学生と看護学生による病棟実習は、どのような内容でしょうか? 【回答4.】 医学科1年次132名早期体験実習と保健学科看護学専攻2年次80名基礎看護実習Ⅰを合同で行います。実習最初のオリエンテーション・関連部署の講義等(2日間)は、1つの講義室で行います。その後は4グループに分かれて、3日間の病院実習(14病棟)と1日のまとめカンファレンスを実施します。合計212名が4グループ/14病棟に分かれますので、各病棟に4名(ないし3名)の学生が配属となります。病棟配属の学生は、医学科と保健学科の混成となります。十分な時間を病棟で過ごすため、医学科・保健学科の学生間でのコミュニケーションもとても良くとれています。まとめカンファレンスでは、病棟実習での経験を踏まえ、各自の学びを学生全員が共有するための討議・グループ発表を行います。医療人としての共通の観点に加えて、医師・看護師独自の観点が議論の対象となることもあります。非常に実りある実習となっています。 【質問5.】 正課の授業の履修により「防災士」の受験資格が得られることはとても魅力的なことと思います。差し支えなければ実際に受験した人数、試験に合格して防災士の資格を得られた人数などをご教示いただけますでしょうか? 【回答5.】 防災士受験資格を得られるように、弘前大学の災害・被ばく医療教育センターと連携し、教養教育科目として2科目を設置しました。2科目のうち、「災害原理と防災」を前期に、「災害医療・情報」を後期に開講し、通年で履修することで、受験資格が得られるようになります。教養教育科目ですので、医学科の学生のみを必修とすることはできませんでしたが、教養教育ガイダンスなどで「医学科学生は履修推奨」との説明を行いました(医学科学生履修用に講義室を配置)。結果として、2023年度は113名全員が履修しています。今年度から開始しましたので、実際に防災士の資格を取得した学生はまだ出ていません。 日本防災士機構のホームページ https://bousaisi.jp/license/ に、防災士資格の取得要件が記載されています。これに従って、2科目の講義内容を構築しますが、大学教員のみならず、県関連の方々なども講義を担当いただくことで、開講することができました。 |
| 第24回 琉球大学の記載事項(R5.9.13記載)への感想・質問 |
|---|
| 【感想】 琉球大学での取り組み「島嶼性を生かし国際性豊かな医療人材育成を目指す琉球大学医学部の教育」について大変興味深く拝読致しました。 様々にご紹介頂いた特色のある取り組みの中で特に、「高大接続事業や先輩医師と学生とを結ぶキャリア相談会などを通じて、高校生、医学部学生、若手医師との繋がりを強化し、医学教育での学習者間のつながりを太くし、教わり教えあう『屋根瓦』文化の醸成」という試みに注目致しました。 今年2023年に、我が国の医学教育は臨床実習前客観的臨床能力試験(Objective Structured Clinical Examination:OSCE)とComputer-based Testing(CBT)からなる医学系共用試験の公的化という大きな転換点を迎えたと言われています。医学生が共用試験に合格していることが医師国家試験の受験要件として法的に定められ、その準備教育のために医学部教員の教育的エフォートが増大することになりました。これに加えて、2024年度からは医師の働き方改革も実施されることから、医学部教員の勤務時間を削減する中で教育的エフォートを増やすという大きなチャレンジと我々は向き合うこととなります。 モデル・コア・カリキュラム令和4年改訂版によると、海外でNear-peer learningと呼ばれる学年の近い上級生(もしくは上級医)が下級生(後輩医師)を教育する手法が、日本国内で伝統的に臨床教育の中で実践された屋根瓦式教育と同義であるとされています。また、同モデル・コア・カリキュラムでは、「生涯にわたって共に学ぶ姿勢」が、10の資質・能力の1つとして定められ、その中に医療者教育の実践として、「後輩や同僚等に対して、適切にフィードバックできる」、「成人学習理論を活用し、後輩や同僚等に対して教育を実践できる」という屋根瓦式教育に関連する学修目標も示されています。この教育手法は、教わる側だけなく教える側にも教育効果があるとされ、さらには教員の教育負担を軽減する利点もあるとされ、日本国内からの卒前・卒後教育における医学教育学的エビデンスも蓄積されつつあるようです。 学生が医学部で学ぶ時期から先輩後輩の中で自然に教え合い、屋根瓦式教育という教授手法がそれぞれのキャリアパスの中でのそれぞれの関わりに浸透し、将来的に地域医療教育実践の日常で展開される中で、不確かな状況でも周囲と協働しながら問題解決を図る地域医療人が育成されていく日をいつか迎えるために、今医学部教員に何ができるか、皆様とディスカッションできればと思っております。 (弘前大学) |
|
ご意見いただき、ありがとうございます 以下、屋根瓦教育について金城個人の私見とはなりますが述べてさせていただきたいと思います 前任の研修病院では、研修医2年目が1年目や医学生を教えることが期待されており、一部の「教え上手・好き」な研修医だけに限定されていませんでした。後輩を指導することが業務の一部となっています。教えることで後輩の力がつけば、後輩に頼めるという負担軽減の要素もありますが、下からの評価を研修医自身が受けるということも大きく影響していると思います。 米国では研修医からの評価が医学生の臨床実習の成績に反映されるため必死に自らを売り込みます。忙しい当直時には入院となった患者の病歴を研修医に先んじて医学生が聴取するといった実務的手伝いから、当直時の弁当の買い出しなど様々な雑務までこなし、当直チームの欠かせない一員に学生がなっていました。 我が国では研修プログラムによっては屋根瓦を形成できるほど人数がいない場合も多いですが、世代が近い先輩というロールモデルがいることは医学生にとっても近未来の目標が見えやすいというメリットがあるように思います。 拙文に写真が掲載されていますが、琉球大学で行ったハワイ大学医学部Kasuya先生、Oomori先生によるPBLワークショップは学年をまたいだグループで症例をディスカッションしました。実に生き生きと皆が参加し、上級生が下級生を助けながら議論をリードしていく力、教え学びあう力が学生自身にあるのだと確信しました。 教官はどうしても老婆心から「自分が教えないといけない」、「学生同士が間違ったことを教えたらいけない」など心配しがちですが、学生の力を信じてやらせてみる度量をわたくし自身が持たなければいけないと感じた次第です。 まだまだ実績があるわけではないですが、琉球大学のなかでも学びの輪が学生の間に広がるよう尽力したいと思っております。 |
| 第23回 旭川医科大学の記載事項(R5.8.23記載)への感想・質問 |
|---|
| 1)地域医療を担う医師それぞれが、自身の望む高いレベルのキャリア形成を実現できるような教育および支援体制を構築する必要性について同感です。 一方で、配置医師の数や専門領域バランスの適正化を図る、という目標を達成するには、マネジメントが必要と考えます。そのマネジメントを統括するのが地域共生医育センター、医局と調整の上で「地域共生医育センター」が主管して行う、という理解でよろしいでしょうか? 対象は地域枠卒業生のみでしょうか? 2)地域毎に異なる課題を抽出し、その解決策を考察する過程での「マルチタスク型地域医療医」の育成という取り組みは興味深いです。この取り組みは地域枠学生のキャリアが連動するのでしょうか? また、領域別プログラムの専攻希望に対応するために、専門医取得後にこのマルチタスク型地域医療医としてのキャリアがスタートする、という理解でよろしいでしょうか? 3)地域共生医育センターは多職種のキャリア支援のために活動する、という理解でよろしいでしょうか? (新潟大学) |
| 【質問1.】 地域医療を担う医師それぞれが、自身の望む高いレベルのキャリア形成を実現できるような教育および支援体制を構築する必要性について同感です。 一方で、配置医師の数や専門領域バランスの適正化を図る、という目標を達成するには、マネジメントが必要と考えます。そのマネジメントを統括するのが地域共生医育センター、医局と調整の上で「地域共生医育センター」が主管して行う、という理解でよろしいでしょうか? 対象は地域枠卒業生のみでしょうか? 【回答1.】 私たちもマネジメントが重要であると思っております。地域共生医育センターが地域のニーズを把握した上で、各講座や医局と協力しながら、バランス良く医師を配置することができる体制を作りたいと考えます。対象は地域枠学生だけでなく、私たちの地域医療構想に賛同するすべての学生です。 【質問2.】 地域毎に異なる課題を抽出し、その解決策を考察する過程での「マルチタスク型地域医療医」の育成という取り組みは興味深いです。この取り組みは地域枠学生のキャリアが連動するのでしょうか? また、領域別プログラムの専攻希望に対応するために、専門医取得後にこのマルチタスク型地域医療医としてのキャリアがスタートする、という理解でよろしいでしょうか? 【回答2.】 地域枠学生に限らず、本学が行う地域医療支援に興味を持ち、参加を希望するすべての学生が対象です。地域枠学生の義務勤務などと連動するものではありません。また、「マルチタスク型地域医療医」という資格認定等は予定しておりません。一定の研修期間を設定するものではなく、研修施設も地域医療ニーズの分析結果などを基に決定されます。地域で役立つ医師になることがゴールであり、その評価は地域によってなされものと考えています。 領域別専門医プログラムとの関係ですが、主に内科専門医、総合診療専門医プログラムを基盤とする地域医療医育成を想定しています。例えば、総合診療専門医プログラムを専攻しながらマルチタスク型地域医療医としての素養を身につけることは、時間的にも効率の良いキャリア形成に繋がり、地域医療の現場においても若い力として貢献するものと考えています。このため、本学の総合診療専門プログラムの連携施設等について適宜見直し、マルチタスク型地域医療医育成に寄与するプログラムになるよう継続的に改良していきます。また、内科専門医については、総合診療専門医とのダブルボードを目指す専攻医などが好適と考えています。本学の救急専門医プログラムには、救急対応能力のある地域医療医を目指している専攻医も多く登録していますが、そのような専攻医にもぜひ参加してほしいと考えています。また、それ以外の専門医については、専門医取得後の参加が多いと想定していますが、そのような医師のリスキリング支援を充実させたいと考えています。 なお、本学の地域枠は、本学の講座(基礎医学講座も可)や診療科などに所属し、本学が行う地域医療支援にいかなる形でも貢献すること、というのが卒後の義務です。 義務勤務(地域枠キャリアプログラム)は設定しておりません。奨学金などは貸与されず、下記AJMCの地域枠分類のB2に該当します。一部、北海道の奨学金を、入学後手上げ方式で希望し貸与を受けている学生もいますが、この学生は北海道の地域枠キャリアプログラムに沿った義務勤務があります。 A:奨学金を支給する制度 A1:別枠で入学選抜を実施し、卒後一定の年数の義務履行を課すもの A2:入学後選抜し、卒後一定の年数の義務履行を課すもの B:奨学金を支給しない制度 B1:別枠で入学選抜し、卒後、一定の年数の義務履行を課すもの B2:別枠で入学選抜するが、卒後の義務履行年数が明示されていないもの 【質問3.】 地域共生医育センターは多職種のキャリア支援のために活動する、という理解でよろしいでしょうか? 【回答3.】 基本的には医師のキャリア支援のための活動です。多職種との連携については地域医療教育の一環として重要な位置を占めますが、地域共生医育センターが多職種のキャリア支援に関わることはありません。 本学看護学科には、看護職キャリア支援センターがあり、看護学生、あるいは道北・道東の看護職者を対象に、大学と病院、地域の保健医療福祉機関との連携を深め、社会のニーズをとらえたキャリア支援を行っています。 |
| 第22回 大分大学の記載事項(R5.7.5記載)への感想・質問 |
|---|
| 1)5年次の地域医療実習で16施設を拠点に、多職種協働や地域包括ケアを学ぶ実習を指導、学んだことをアウトプットする振り返りを実施し、指導医と情報交換をする点が素晴らしいと感じました。この実習の学外指導医はどのような診療科の先生が担当しているのでしょうか? 2)また、この学外実習中に、地域医療学センターのスタッフは現地でも関わっているのでしょうか? 3)地域医療学センターの教員8名は、専任でしょうか、兼任でしょうか? 兼任の場合、エフォート配分はどのようになっていますか? 4)学外医療機関、介護施設の指導者を集めてのFDは、どの時間帯に何時間、どのような頻度で行っているのでしょうか? また会場は大学なのか、どのような職種の方が何名くらい集まるのか、などご教示ください。 5)地域枠同門会「地域医療の明日を拓く会」はとてもよいアイディアと思います。どこが主導してこの会を立ち上げたのか、また継続するための工夫や支援についてお教えください。 (新潟大学) |
| 【質問1.】 5年次の地域医療実習で16施設を拠点に、多職種協働や地域包括ケアを学ぶ実習を指導、学んだことをアウトプットする振り返りを実施し、指導医と情報交換をする点が素晴らしいと感じました。この実習の学外指導医はどのような診療科の先生が担当しているのでしょうか? 【回答1.】 ご質問をいただき、ありがとうございます。地域医療実習の学外指導者は、さまざまな診療科の医師が担当しています。総合診療科の先生もおられますが、消化器外科であったり、小児科であったり、それぞれに専門をお持ちの先生が多いです。 【質問2.】 また、この学外実習中に、地域医療学センターのスタッフは現地でも関わっているのでしょうか? 【回答2.】 地域医療学センターのスタッフは、現地ではほとんど関わっていません。基本的には実習病院にお任せをしています。実習がすべて終わった後に、実習施設の関係者とスタッフとが実習の振り返りを行う機会を設けています。 【質問3.】 地域医療学センターの教員8名は、専任でしょうか、兼任でしょうか? 兼任の場合、エフォート配分はどのようになっていますか? 【回答3.】 地域医療学センター8名のうち教授2名と准教授2名は総合診療・総合内科学講座、および総合外科・地域連携学講座の所属で、兼任です。センター開設時はセンターのエフォートが80%程度でしたが、現在の1年間を通してのエフォートは講座80%、センター20%くらいです。しかし、多くの仕事はオーバーラップしています。助教4名は地域医療学センターの所属ですが、講座の診療・教育業務にも関わっています。 【質問4.】 学外医療機関、介護施設の指導者を集めてのFDは、どの時間帯に何時間、どのような頻度で行っているのでしょうか? また会場は大学なのか、どのような職種の方が何名くらい集まるのか、などご教示ください。 【回答4.】 地域医療実習に関するFDは年1回です。コロナウイルス感染症のため対面で行うことができなかったため、最後に行えたのは令和元年でした。9月から実習が始まるため、7月ごろまでに実習のスケジュールを提出いただき、手引きを作成する必要があります。そこで、5-6月ごろにFDを行い、この実習を含めた大学のカリキュラムについての説明や、地域医療実習で学生の評価が高かった取り組みの紹介などを行い、参考にしていただいていました。 令和元年は、6月の土曜日の午後3時間、公共施設の会議室を使って行いました。実習責任者である病院長をはじめ、実習を担当していただいた医師が25人程度、学生担当の事務職員が15人程度、併せて40人ほどにお集まりいただきました。この時には、医師以外の他職種の方にはお声がけしていませんでしたが、各実習施設との個別の振り返りの際には、他職種の方にもご参加いただいています。 【質問5.】 地域枠同門会「地域医療の明日を拓く会」はとてもよいアイディアと思います。どこが主導してこの会を立ち上げたのか、また継続するための工夫や支援についてお教えください。 【回答5.】 立ち上げたのは地域医療学センターです。第1回目の同門会総会で地域枠医師から会長を選出し、地域枠医師と地域枠学生主導の会に移行する過程にありましたが、コロナ禍で会合を持つ機会が3年間持てなくなり、今年3年ぶりに総会を開催する予定です。今年は地域枠医師で「拓く会」の世話会を立ち上げ、今後の方向性を検討することとしています。地域医療学センターは、会の開催に係る段取りや会員への連絡、経済的な支援を行っています。 |
| 第21回 信州大学の記載事項(R5.6.21記載)への感想・質問 |
|---|
| 1)「診療科に関わらず地域のニーズを考え診療の場にあった医療を能動的に実践できる人材養成へ変革すべき」という点に強く共感します。「能動的な人材」育成のために特に力を入れている実習などありましたらご教示下さい。 2)「地域医療」授業は、来年度以降4年次の必修科目となり、授業時間がこれまでの4コマから大幅に拡充されるとのことですが、どの程度増えるのか、またその統括を行うのは寄附講座の地域医療推進学講座なのか、ご教示ください。 3)地域枠入学者への卒前プログラムは、どの組織が管理しているのか、一般枠学生は聴講できるのか、様々な診療科の医師が講義に関わっているのか、ご教示ください。 4)卒前卒後のシームレスな医学教育を行ううえで、卒後の地域枠医師への関与はどのように行っているのか、ご教示ください。 (新潟大学) |
| 【質問1.】 「診療科に関わらず地域のニーズを考え診療の場にあった医療を能動的に実践できる人材養成へ変革すべき」という点に強く共感します。「能動的な人材」育成のために特に力を入れている実習などありましたらご教示下さい。 【回答1.】 長野県は300床程度の小規模病院が地域医療の中核となっています。このような病院は、同時期に多数の学生を受け入れることは困難であるものの、診療科毎に1名の学生であれば通年で受け入れ可能な環境にあります。そこで、医学部附属病院および県内の教育協力病院の要望を取り入れ、5年次後期にレディーメイドの研修プログラムを150通り以上設定し、その中から学生に1つを選択させることで現場に負担をかけることなく72週間の臨床実習を実現しています。 【質問2.】 「地域医療」授業は、来年度以降4年次の必修科目となり、授業時間がこれまでの4コマから大幅に拡充されるとのことですが、どの程度増えるのか、またその統括を行うのは寄附講座の地域医療推進学講座なのか、ご教示ください。 【回答2.】 16コマに増えます。当教室が統括いたします。 内容は未決定ですが、令和4年度の医学教育モデルコアカリキュラムのキャッチフレーズにあるように現代の社会背景に考慮した幅広い領域をカバーできる授業を目指しています。 【質問3.】 地域枠入学者への卒前プログラムは、どの組織が管理しているのか、一般枠学生は聴講できるのか、様々な診療科の医師が講義に関わっているのか、ご教示ください。 【回答3.】 地域医療推進学教室が管理しています。地域枠限定です。 医学部・附属病院以外から講師を招聘しています。 今年度内容です。 5月:地域に根ざした医療の実践 伊那市国保美和診療所所長 岡部竜吾先生 6月:地域での在宅ケア・ACP 市立大町総合病院家庭医療科 金子一明先生 7月:コロナ禍での医療体制 経法学部教授 増原宏明 先生 8月:ヤングケアラーとして 美齋津康弘 さん 9月:対話型鑑賞 ミルキク代表 森永康平 先生 10月:視覚障害者として考えるソーシャルインクルージョン 広沢里枝子 さん 11月:臨床倫理 講師未定 12月:在宅ホスピス ふじ内科クリニック 内藤いづみ 先生 【質問4.】 卒前卒後のシームレスな医学教育を行ううえで、卒後の地域枠医師への関与はどのように行っているのか、ご教示ください。 【回答4.】 長野県医学生修学資金貸与医師に対して (1)年に1回の面談:現在の研修・勤務について、今後の配置病院について (2)夏季交流会の開催:医学生との交流 医学生への専門科別キャリアの説明 (3)ブラッシュアップセミナーの開催:臨床能力を伸ばすための学習会 (4)症例発表会・症例検討会の開催(令和6年度予定) |
| 第20回 高知大学の記載記事(R5.5.24記載)への感想・質問 |
|---|
| 現在の日本の状況と医育大学の役割について一般論として語っている部分ですが分かりやすく正鵠を得ていると思いました。「地域の医療機関に学生が繰り返し赴く機会を設けること、とくにクリニカル・クラークシップでは統合的、診療参加型の実習に変革していくことが必須であると考えている。」は強く共感します。 1)貴学の臨床実習は、学外のみでの診療参加型実習という理解でよろしいでしょうか。 2)この場合、学内と学外の同一診療科で教育内容と実習方針のマネージはどのようにしていますか? 3)学内臨床科医師の指導力の維持向上はどのように図られていますか? 4)地域枠卒業医師の、卒後の指導力向上のための取組がございましたらご教示ください。 5)「家庭医道場」「幡多地域医療道場」といった課外実習の参加者(学部、学年)、規模、使われている資金などをご教示ください。 6)「ポストコロナ時代の医療人材養成拠点形成事業」で「黒潮医療人養成プロジェクト」が採択されたとのことですが、和歌山県立医大、三重大学と医学生が交流するような事業はありますか? 7)9年間の義務年限終了後の地域枠卒業生の県内残留率をご教示ください。 (新潟大学) |
| 【質問1.】 貴学の臨床実習は、学外のみでの診療参加型実習という理解でよろしいでしょうか。 【回答1.】 高知大学の臨床実習は4年次3月より5年次2月まで(44週)の臨床実習Ⅰと、5年次3月より6年次7月まで(19週)の臨床実習Ⅱとなっております。臨床実習Ⅰは1~2週間単位で25診療科のローテーション、関連教育病院3週間、後者は学生の希望と調整し学外も含め3~4週間単位×5クールで実施しております。 これら臨床実習Ⅰ、臨床実習Ⅱのすべての期間をクリニカル・クラークシップとしておりますが、学生が診療参加型で実習できているかどうかは、実習先によって温度差があるものと承知しております。今年度から臨床実習Ⅱを従来の1~2週単位から4週単位(一部3週)に変更したのも診療参加型として充実していくことを狙ったものです。その効果については、現在、検証中です。 【質問2.】 この場合、学内と学外の同一診療科で教育内容と実習方針のマネージはどのようにしていますか? 【回答2.】 大学病院と関連教育病院では自ずと医療の役割が異なります。同一診療科であっても、疾患の構成、患者の背景なども異なりますので、学生にはありのままを実習していただくようにしております。 大学と関連教育病院との連携は「関連教育病院運営協議会」の場で、全般的な課題についての協議を行っており,診療領域毎の調整などは実施していません。 今後は疾患分類や経験症例のデータ集積と分析によって、実績に基づいた実習先の調整が可能になろうかと考えています。 【質問3.】 学内臨床科医師の指導力の維持向上はどのように図られていますか? 【回答3.】 ご指摘のように指導医のFDは大変重要であると存じます。一方で、指導医が多忙であり、FDとしてまとまった時間をとることはなかなか困難です。十分とは言えませんが、講習会の開催、臨床研修指導医養成ワークショップ(年2回開催)などの機会を通じて指導力の維持向上を目指しております。 教員のFDとして、必ず受講すべき基礎講習と発展講習を設定しています。基礎講習は全教員に年1回受講を義務づけ、医学科のカリキュラム全体の理解を主な目的として主にe-learningで実施しています。発展講習は、教員の教育能力の向上に寄与することを目的とし、教員は自らのエフォート率を考慮し自己研鑽のために受講することとしています。発展講習は対面での実施を原則としていますが、可能な限り録画等を行い、e-learningでも受講できるようにすることで、忙しい指導医でも受講できるよう配慮しています。 【質問4.】 地域枠卒業医師の、卒後の指導力向上のための取組がございましたらご教示ください。 【回答4.】 地域枠卒業医師に限定した指導力向上の取組はございません。 【質問5.】 「家庭医道場」「幡多地域医療道場」といった課外実習の参加者(学部、学年)、規模、使われている資金などをご教示ください。 【回答5.】 「家庭医道場」は高知県からの寄附講座である家庭医療学講座が主催しております。参加者は特に地域枠には限定してはおらず、医学科、看護学科のすべての学年を対象としております。年2回、県内の中山間地にバスで赴き、医療施設の見学、グループワーク、フィールドワークなどをおこなっています。参加者は、1回あたり30~40人程度です。実施に当たっては、自治体、医療施設、JA等の企業、住民組織等のご協力をいただいております。資金は、家庭医療学講座の活動として高知県、市長会・町村会からいただいている寄附金を使わせていただいております。 「幡多地域医療道場」も当初は家庭医療学講座が主催しておりましたが、今は高知地域医療支援センターが主催しております。1~4年次の地域枠/奨学金受給学生のみを対象としております。参加者は、1回あたり40人程度、夏期休暇中に2泊3日で、バスで高知県西部の幡多医療圏に赴き、県立幡多けんみん病院、四万十市立市民病院等に分かれて実習します。夜は、幡多医師会の協力もいただき、地域医療シンポジウム、意見交換会の開催もおこなっております。地域医療シンポジウムは、医師会の先生方にもご参加いただくほか、県教育委員会、県内私立高校にも周知し、数名の高校生が参加することもあります。資金は、高知県からの地域医療支援センターの事業費の他、懇親にかかる部分につきましては、幡多医師会、高知大学医学部同窓会、教授会からのご寄附により賄っております。 「家庭医道場」「幡多地域医療道場」ともに2020年度以降、コロナ禍により中止を余儀なくされています。2023年度から再開するよう準備しております。 2022年度から文部科学省の補助事業「ポストコロナ時代における医療人材養成拠点形成事業」により、正課の「臨床体験実習(1~3年次)」で幡多けんみん病院を含む地域医療人材養成拠点病院の実習を可能となるように順次拡大するに伴い、幡多地域医療道場は2024年度で終了する予定です。 地域枠/奨学金受給学生には1~4年次に各学年で1回以上、何らかの地域医療に関するプログラムに参加し、レポートを提出することを要件としております。上記の「家庭医道場」「幡多地域医療道場」「臨床体験実習」のいずれもそのプログラムとして認められているものです。 【質問6.】 「ポストコロナ時代の医療人材養成拠点形成事業」で「黒潮医療人養成プロジェクト」が採択されたとのことですが、和歌山県立医大、三重大学と医学生が交流するような事業はありますか? 【回答6.】 本事業は2022年度から開始され、取組は緒に就いたばかりです。本事業の実効性を高めるにあたり教員や学生の交流は非常に重要なことだと考えております。各大学に設置されたコースの責任者間での検討、事業推進委員会の協議を経て取組を強化していく方針です。 年1回、合同オンラインシンポジウムを三大学持ち回りで開催することとしております。各大学から教員、学生がオンラインで参加する他、本プロジェクトのコースを履修した学生が開催地に集まり、成果を報告する予定です。2023年3月に高知大学で開催した第1回のシンポジウムでは、和歌山県立医科大学、三重大学から数名の学生が来県し、意見交換をおこなったほか、防災施設等の見学ツアーをおこないました。 各大学で複数年次に跨るアクティブラーニングコース(地域総合診療、医療DX、感染症・災害救急)を準備しております。各コースの責任者間で協議し、交流の機会を計画的に設けます。地域総合診療コースの学生は毎年、学会の場での交流を計画しています。第14回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会(2023年5月13、14日、名古屋市)において、ポスターツアーを企画し三大学から学生10人が参加し、交流しました。また、感染症・災害救急コースでは、2023年8月に高知県での災害現場ツアー・津波避難タワー宿泊実習、2023年10月には高知県での大規模津波災害医療対策訓練、三重大学医学部附属病院防災訓練に相互に学生を派遣し、交流する計画です。 6年次では各大学で県内の地域医療人材養成拠点病院での長期滞在型クリニカル・クラークシップを実施いたします。三大学で相互に学生を派遣することとし、2023年度は6人の学生が自県以外の拠点病院でのクリニカル・クラークシップをおこないます。拠点病院では他大学の学生とも交流する他、共同でオンラインでのオリエンテーション、振り返りをおこなうなど派遣元・派遣先の教員も交えた交流をおこなっています。 【質問7.】 9年間の義務年限終了後の地域枠卒業生の県内残留率をご教示ください。 【回答7.】 まだ、現時点において卒業後9年間の義務年限が終了した地域枠医師はおりません。今年度末から順次、終了者が出る見込みです。 |
| 青森県は医師不足県であり、学外実習施設は診療がかなり忙しい上に、臨床実習学生を引き受けて頂いており、なかなか細かい点を要求しづらいと感じています。このため、以下の質問をさせて頂きます。 8)貴学の臨床実習は、学外でも診療参加型実習を行っておられますが、学外実習施設の指導教員による実習評価とそれに基づく学生へのフィードバックを、大学病院と連動して行うことをJACME受審時に求められたと思いますが、その点は、どの様に行っているでしょうか? 9)臨床実習の改善を継続して行って行くにあたり、学外施設の指導教員の意見も取り入れて行く必要がありますが、その点はどのようにして取り入れ反映されているでしょうか。 (弘前大学) |
| 【質問8.】 貴学の臨床実習は、学外でも診療参加型実習を行っておられますが、学外実習施設の指導教員による実習評価とそれに基づく学生へのフィードバックを、大学病院と連動して行うことをJACME受審時に求められたと思いますが、その点は、どの様に行っているでしょうか? 【回答8.】 当学では臨床実習の評価は、卒業時に獲得すべき資質・能力(コンピテンシー)に沿ってルーブリック評価を行っており、同じルーブリックで学生の自己評価と指導医の評価をe-ポートフォリオ上で共有しており、学生、教員への相互フィードバックとなっています。その一方でe-ポートフォリオが大学全体のシステムであるため学外指導医がアクセスできず、学外臨床実習は紙ベースのルーブリック評価となっており、e-ポートフォリオを介したフィードバックはできていません。事務職員による代行入力について検討中です。 【質問9.】 臨床実習の改善を継続して行って行くにあたり、学外施設の指導教員の意見も取り入れて行く必要がありますが、その点はどのようにして取り入れ反映されているでしょうか。 【回答9.】 学外施設の指導医からは、毎年、実習に対するご意見、大学に対するご意見を収集しており、医学教育IR室で分析し、医学教育プログラム評価委員会の検討を経て、医学科カリキュラム委員会、臨床実習部会にフィードバックされます。また臨床実習部会の委員は診療科からは参加していないため、講座・診療科の教育担当者が集まる教育主任会議で情報共有し、実習の改善点策を臨床実習部会、医学科カリキュラム委員会に上げる仕組みになっています。なお臨床実習部会には、実習受け入れ施設の指導医が2名、外部委員として参加しています。 |
| 第19回 東北大学の記載記事(R5.4.27記載)への感想・質問 |
|---|
| 臨床研修での医師養成と地域医療への貢献を目的に協議会を設置した点が興味深いです。 1)NPO法人艮陵協議会では、加盟11道県118機関を対象とする指導医講習会をされており、効率的な取り組みであると感じました。千葉県の病院等も加盟していますが、加盟要件を教えてください。 2)艮陵協議会の設置が東北7県の研修医数の変化に与えた影響をどのように評価しておられますか? 3)「艮陵協議会と地域医療行政とのずれ」が生じているとのことですが、学生実習に関わる費用関連の他にはどのような問題があり、どのような対応が必要とお考えでしょうか? 4)艮陵協議会と各都道府県の各大学の医学部との連携を教えてください。 5)看護科と合同の多職種連携ワークショップの実際についてご教示ください。 6)総合診療サークル「Team COOL」の具体的な活動についてご教示ください。 (新潟大学) |
| 【質問1.】 NPO法人艮陵協議会では、加盟11道県118機関を対象とする指導医講習会をされており、効率的な取り組みであると感じました。千葉県の病院等も加盟していますが、加盟要件を教えてください。 【回答1.】 NPO法人になった時点で、加盟する要件は、定款(http://www.gonryo.com/info/rules.html)に定められております。加盟病院は定款上では団体正会員となります。 第6条 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体団体正会員の入会金は1万円、年会費は7万円となっております。 法人の目的に賛同していただければ、どなたでもどの病院でも入会することができます。 【質問2.】 艮陵協議会の設置が東北7県の研修医数の変化に与えた影響をどのように評価しておられますか? 【回答2.】 艮陵協議会の歴史は1968年のインターン闘争にまでさかのぼり、非入局自主ローテートを研修医、加盟病院、大学の三者がそれぞれ対等の立場で初期研修のありかたを追及した結果できた任意団体「三者協議会」を2008年にNPO法人化したものです。その目的は、(1)特定非営利活動に係る事業、(2)指導医の確保と養成に関する事業、(3)研修医の確保と育成に関する事業、(4)地域医療に従事する医師の支援に関する事業(5)医学・医療の発展を支援するための事業、(6)地域医療の充足に関する事業などの実施です。この歴史的な継続性は2004年にはじまった卒後初期臨床研修のモデルのひとつとなりました。5年ごとに見直される初期臨床研修制度にも対応しながら、これまでに1,000名以上の臨床研修指導医を認定し、どの大学の学生でも参加可能な合同病院説明会を開催し、研修医および指導医の臨床技術の向上と標準化などを実施しています。三者協議会設立当初から、東北大学を卒業し、艮陵協議会の加盟病院で研修する学生は卒業生の60%近くを占めておりますので、50年以上前から屋根瓦式の研修および研修指導、研修終了後の大学への人材還流、指導医の派遣が行われてきました。艮陵協議会(三者協議会)がなかったならば、東北地方で研修する研修医の数と質は大きく異なっていたと考えます。 【質問3.】 「艮陵協議会と地域医療行政とのずれ」が生じているとのことですが、学生実習に関わる費用関連の他にはどのような問題があり、どのような対応が必要とお考えでしょうか? 【回答3.】 地域医療に関する制度設計や補助金交付等は都道府県単位であり県境を越えた対応は想定されておりません。また、岩手県、山形県、宮城県を除いては艮陵協議会が地域医療制度に関与するための公式の場は設けられていません。すなわち、それぞれの県の地域医療対策協議会の当該県の中で閉じており、東北全体の医師配置を議論する場が存在しない点が問題であると考えます。地域性や各大学の診療科の事情などを鑑みて、東北全体で医師配置を議論する場が必要のように思います。 【質問4.】 艮陵協議会と各都道府県の各大学の医学部との連携を教えてください。 【回答4.】 艮陵協議会は東北大学を中心に発展してきましたが、NPO法人には定款どおり、設立趣旨に賛同できる方はどなたでも、どの団体でも参加することができます。各加盟病院は北海道から関東におよぶため、各所在地の大学との関係も良好に保つ必要があります。人口減少に直面する今日、競いあいながらも協力しあって医学部から卒後初期臨床研修、後期研修(専攻医)、指導医へとシームレスにキャリアを重ねていくことを支援できればと考えております。各種セミナー、臨床研修指導医講習会への参加は加盟病院からの申し込みを優先していますが、出身地、出身大学は無関係です。合同病院説明会の案内は東北の各医学部に送付しています。セミナーの講師も各地からおいでいただいております。 【質問5.】 看護科と合同の多職種連携ワークショップの実際についてご教示ください。 【回答5.】 医学科1年生・看護学科1年生を対象とした医療安全を題材にした半日枠でのワークショップです。患者取り違え、筋弛緩薬の誤注入、患肢の左右取り違えに伴う健康側の四肢の切断という実際に起きた事例について、その原因や改善策をグループ内で討論し、それぞれが全体会で発表し全体討論を行う形で実施しております。 【質問6.】 総合診療サークル「Team COOL」の具体的な活動についてご教示ください。 【回答6.】 最初に、総合診療サークルTeam COOLが、コロナ禍で活動を縮小し臨床推論サークルTeamCoolと名称変更したことを認識せずに記述し、誤解を与えましたことをお詫び申し上げます。本サークルは、文科省事業「リサーチマインドを持った総合診療医の養成(H25-29)」に本学が採択されたことを契機として、同事業に学部生を参加させたことで設立されました。2019年頃までは「東北どまんなか~総合診療勉強会~」を定期的に主催し、夏休み等に高名な総合診療医を招聘し、東北地方の医学生や保健学科学生100名程度が参加する総合診療勉強会を実施するなど、精力的に活動しておりました。しかし、コロナ禍によって対面による活動を自粛したことから活動範囲が東北大学内までに縮小し、さらに、昨年度からは臨床推論サークルに名称を変更し臨床推論の勉強会を開催するにとどまっております。 |
| 第18回 長崎大学の記載記事(R5.4.7記載)への感想・質問 |
|---|
| 1)地域医療教育で実績のある貴学が進める、「地域の枠をこえた地域医療教育の展開」は素晴らしいと感じました。「ポストコロナ時代の医療人材養成拠点形成事業」では長崎、熊本、鹿児島の3大学の学生が相互に交流する実習を行うとのことですが、具体的にどの様な実習を行うのでしょうか?
またそれは正課の臨床実習でしょうか? 2)地域基盤型医学教育等で、遠隔診療についての講義や実地体験などの機会を設けておられますでしょうか? 3)地域枠推薦入試の出願要件に「地域医療ゼミナール」の受講を加えているとのことですが、これは高校生であればどの学年でも受講が可能なのでしょうか? それとも受験学年の3年生だけ? この効果についてどのように評価しておられますか? 4)多職種連携教育の実際についてご教示頂けますと幸いです。 (新潟大学) |
| 【質問1.】 地域医療教育で実績のある貴学が進める、「地域の枠をこえた地域医療教育の展開」は素晴らしいと感じました。「ポストコロナ時代の医療人材養成拠点形成事業」では長崎、熊本、鹿児島の3大学の学生が相互に交流する実習を行うとのことですが、具体的にどの様な実習を行うのでしょうか? またそれは正課の臨床実習でしょうか? 【回答1.】 正規の臨床実習です。各大学が5、6年次に行なっている臨床実習の中で大学外の地域病院実習をこれに当てはめました。大学間教育協定を結び、当然実習成績は進級や卒業判定に反映されます。期間は現時点で1週間です。内容は受け入れ先のスケジュールに沿って指導していただきます。 【質問2.】 地域基盤型医学教育等で、遠隔診療についての講義や実地体験などの機会を設けておられますでしょうか? 【回答2.】 今後、遠隔診療は特に離島診療で必須のツールになると考えられ、将来離島勤務が想定される本学の学生にはその様子を研究段階も含めて講義で示しています。また、五島中央病院内に設置している長崎大学離島医療研究所の教員が離島実習で指導する際に、遠隔診療の現場に同席させることもあります。今後、このような機会を増やしていく予定です。 【質問3.】 地域枠推薦入試の出願要件に「地域医療ゼミナール」の受講を加えているとのことですが、これは高校生であればどの学年でも受講が可能なのでしょうか? それとも受験学年の3年生だけ? この効果についてどのように評価しておられますか? 【回答3.】 「地域医療ゼミナール」の受講を地域枠推薦入試の出願要件としていることもあり、対象者は受験資格と同様に長崎県出身者で、同年度の卒業見込みの3年生と卒業生(1浪まで可)が対象です。導入後に地域枠出願者の増加がみられましたが、共通テストなど入試制度の変革もあり現時点で制度の効果は不明です。質的な効果測定は入学後の学業成績や離脱率の変化を検証することになるため、今しばらく時間を要します。 【質問4.】 多職種連携教育の実際についてご教示頂けますと幸いです。 【回答4.】 本学は医学部(医学科、保健学科)、歯学部、薬学部を有するため、医療系学科間で低学年から共修の学習機会を設けています。学年に応じて講義、演習、実習を織り交ぜ、徐々に臨床現場に近接した内容になっていきます。また、2年次には福祉系大学(長崎純心大学)と事例検討のグループ学習(270名、50グループ)により、本学にない社会福祉的視点の涵養を目指しています。臨床実習前の4年次には医学部(医学科、保健学科)、歯学部、薬学部による臨床事例の検討をグループワーク(320名、50グループ)で行なっています。いずれも必修授業です。臨床実習では離島実習において医学科と保健学科、あるいは医学科と薬学部が地域の医療施設で合同実習の機会を設けていますが、こちらはスケジュールがマッチすればということで全員ではありません。 |
| 第17回 新潟大学の記載記事(R5.3.6記載)への感想・質問 |
|---|
| 1)読ませて頂き、勉強になりました。有難うございました。 本筋から外れた質問になりますが、「2. 地域枠の新設・拡大」で、「令和5年度の40名の定員中、全国の高等学校まで対象を広げた定員を18名確保」とあります。当大学では、この枠の学生が一番離脱を希望し、対応に追われることが多いです。他県出身の青森県定着枠の学生には、初めから離脱を念頭に入学して来る者や、在学中に徐々に地元に戻りたい気持ちが強くなる者がおります。新潟大学では、離脱を防ぐための何か特別な教育上の工夫があれば、具体的に教えて下さい。当大学では、入学時と臨床研修スタート時に誓約書や確約書を提出させ、更に学務委員が毎年面接などを行ったり、医学部長からクリスマスカードを送る等の離脱を防ぐ努力はしていますが、100%防ぐことは出来ておらず、昨年、今年と不同意離脱者を出している状況です。宜しくお願い致します。 (弘前大学) |
| 【回答1.】 他県出身の地域枠は2021年度入学生から設定しました。彼らは令和5年4月から3年生になりますので、まだ実績は出ておらず、今後離脱を希望する学生が出てくる可能性は否定できません。 しかし、他県出身に限らず地域枠医学生の離脱をなるべく少なくするためにいくつか心がけていることがあります。それは固定された教員(地域医療支援センター医学科分室教員)による毎年の面談や、その際に、将来の希望をきめ細かく聞くなどしていることです。これらの希望は地域医療支援センター内で共有され、必要に応じて対応が検討されます。 また地域枠医学生を対象として、地域枠医学生に特化した各科からのキャリアパス説明会が行われています。その説明会では地域枠卒業生が各科に入局した場合、地域枠としての義務を果たしながら選択できるキャリアパスについての説明が行われています。その中では専門医の取得に対しての実際の遅れなども具体的に示されています。このように、地域枠としての不利な点も示しながら、一方で地域にいかに貢献できるのかを示すことで地域枠学生の不安を払拭するようにしています。 結果として本県では地域枠卒業生の離脱率が低いですが、その他の理由として、卒後のキャリアパスについて、医局、行政とが連携して対応していることが挙げられます。卒業後は地域医療支援センター医師がメンターとなって一人一人の地域枠卒業生と面談を繰り返し、様々な提案を行いつつ、最大限、地域枠卒業生の希望が叶えられるよう医局と相談する体制にあります。また診療科の制限がないこと、卒後5年目以降は大学院進学や、海外留学なども、義務年限の一時中断はあるものの、基本的に可能となっていることなど、地域枠卒業生がきちんと義務を果たせる環境作りが進められています。 |
| 2)地域枠を増員する中で県外からの枠も増加させているが、他の大学では定員の未充足、そして高い離脱率が問題となっていると聞いている。定員の充足はいかがか、そして離脱防止の具体的な対策を教えていただきたい。 3)新潟方式総合診療医育成コースについて、他の学生たちと完全に分離したカリキュラムなのか、あるいは部分的に分かれているのか、教えていただきたい。別カリキュラムだと、教員の負担がかなり大きくなると思うが、どのように工夫されているのか。宜しくお願い致します。 (岐阜大学) |
| 【質問2.】 地域枠を増員する中で県外からの枠も増加させているが、他の大学では定員の未充足、そして高い離脱率が問題となっていると聞いている。定員の充足はいかがか、そして離脱防止の具体的な対策を教えていただきたい。 【回答2.】 令和5年度入試では、地域枠40名(うち県内枠22名)に対し、県内から112名、県外から43名の受験があり、県内から33名、県外から7名が入学予定です。令和4年度は、地域枠33名(うち県内枠22名)に対し、県内から103名、県外から22名の受験があり、県内から28名、県外から5名が入学しました。 離脱しないための取り組みについては回答1をご覧ください。これまでに94名の地域枠学生が卒業し、1名が臨床医以外への進路変更で離脱しました。他に医学部退学により義務履行できなかったものが1名いますが、県外への離脱はありません。 【質問3.】 新潟方式総合診療医育成コースについて、他の学生たちと完全に分離したカリキュラムなのか、あるいは部分的に分かれているのか、教えていただきたい。別カリキュラムだと、教員の負担がかなり大きくなると思うが、どのように工夫されているのか。宜しくお願い致します。 【回答3.】 新潟方式総合診療医育成コースは、(1)総合診療を専門とする医師、(2)領域別の専門医であっても総合的な診療ができる医師、を卒前・卒後の教育によって養成するカリキュラムです。 卒前教育では、医学部の全学生(収容定員768名)を対象とする正課の中で、1年次の総合診療学入門、2, 3年次の多職種連携実習や臨床推論、医療におけるヒューマンスキル、4年次のObjective Structured Clinical Examination (OSCE) 、総合診療学実習に向けた総論、5-6年次を対象とした臨床推論実践編、診療録記載法、など卒前総合診療コースの教育を行っています。 4-5年次学生全員(約120名)が実習する臨床実習Ⅰでは本講座で臨床推論、症候学、診断学、プレゼンテーションの講義、エコーの実習を行ったのちに、総合的な診療を行う研修指導医(新潟大学医学部臨床教員)が常勤する医療機関で2日間、初診外来を中心とする診療参加型実習を行います。そして、実習で経験した症例を本講座の教員と共に振り返り、レポートとしてまとめ、フィードバックをする過程で、患者の生活背景から、症候、疾患の詳細などを教員と学習しています。 5-6年次の選択制の臨床実習IIでは、学生の実習へのニーズと指導医のシーズをマッチングし、事前に実習内容を双方向性に綿密にコーディネートして診療参加型実習を実施しています。多施設の実習学生、指導医、本講座の教員が、実習中にオンラインで知識や経験を共有し、最終日には指導医がオンラインで参加するハイブリッド形式で経験症例に関する知識・技術を共有することで学びを深めています。実習後の学生・指導医相互の評価とフィードバック、具体的な改善策の共有、というサイクルで継続したことで、この実習IIを選択する学生は、令和2年度に31名(学年全体137名の23%)、令和3年度に51名(学年全体126名の40%)、令和4年度に63名(学年全体121名の52%)と着実に増加しています。さらに令和4年度には、複数の関連病院で、総合診療実習II経験者の研修医と実習生の屋根瓦方式の教育体制が構築され、総合診療教育の拡充にも寄与しております。 教員の負担は軽いとは言えませんが、学生の向学心を大切にしながら、コミュニケーションを大切にして指導しています。 (上記1~3の回答につきましては、令和5年3月時点での内容になります。) |
| 第16回 北海道大学の記載記事(R5.1.26記載)への感想・質問 |
|---|
| 1)4年次の地域医療学は地域の第一線で活躍する先生方を招聘して、学内で講義形式の授業を行う、という理解でいいでしょうか? 2)5年次の地域診療機関での参加型実習の、全体の期間、各クールの期間をご教示ください。 3)オンラインで参加する「地域医療学実習」ですが、地域の診療所や訪問診療の現場をカメラ中継するような形でしょうか? 4)道内三大学が共通の評価表を用いておられるとのことですが、三大学の学生が地域の医療機関で同時に実習し、交流しているという理解でよろしいでしょうか。 5)共通の評価票を用いることで得られたメリットについてご教示ください(例えば、各大学の教育の過不足を見出すことができた、など)。 6)臨床研修の「たすきコース」では、一年目にプライマリケアを学ぶために学外病院での研修を専攻されるとのことですが、このコースを選択する医師の進路(専攻)を可能な範囲でご教示ください(例、3年目以降は専門系の専攻が多い、など)。 7)鹿児島大学病院と連携する広域プログラムはとても興味深いです。これまでの実績についてご教示ください。 8)「国際的医療人育成プログラム」や「CLARCプログラム」の選択者についてもご教示いただけますでしょうか? 9)CLARCプログラムは、マッチング協議会が設定する「臨床研究医コース」との差別化はどの様に為されるのでしょうか? (新潟大学) |
| 【質問1.】 4年次の地域医療学は地域の第一線で活躍する先生方を招聘して、学内で講義形式の授業を行う、という理解でいいでしょうか? 【回答1.】 その通りです。今の科目責任者の前から続いている特色ある試みです。広大な北海道の地で、一生懸命、現場で活躍する先生に教育者としての活躍の場を設けたいという意図があって始まったものです。コロナ禍では、講義をオンラインで行っていただきましたが、コロナ禍明けからは、コロナ禍以前と同様に、各講師に大学に来ていただいて授業を行う予定です。各講師も、医学生への授業について、大変、楽しみにしていらっしゃいます。 【質問2.】 5年次の地域診療機関での参加型実習の、全体の期間、各クールの期間をご教示ください。 【回答2.】 5年次コア科実習は、9月から始まって翌年の3月まで、1クール4週間×6クール=計24週間で行われます。各クールで、学内内科、学外内科(総合診療科含む)、外科、小児科、産婦人科、精神科の計6科を回ることになります 【質問3.】 オンラインで参加する「地域医療学実習」ですが、地域の診療所や訪問診療の現場をカメラ中継するような形でしょうか? 【回答3.】 その通りです。これは今の科目責任者になってからの新たな試みで、コロナ禍ということもあって、現地に医学生100人を派遣するのは難しい状況の中、何とか地域医療の現場を見せる実習ができないかという意図から、地域の診療所や訪問診療の現場をカメラ中継するようになったものです。例えば、訪問診療では、担当医が実際に訪問している患者さんからのメッセージが、生の声として、現場より医学生に中継されることになります。 【質問4.】 道内三大学が共通の評価表を用いておられるとのことですが、三大学の学生が地域の医療機関で同時に実習し、交流しているという理解でよろしいでしょうか。 【回答4.】 各実習施設に派遣される期間が道内三大学で重なっていないことから、同時に三大学の学生が同一施設に出入りして交流を行う機会は残念ながらございません。しかしながら、道内3大学医学教育担当者会議で、各施設への派遣や実習状況等の情報が各大学の医学教育担当者に共有されております。 【質問5.】 共通の評価票を用いることで得られたメリットについてご教示ください(例えば、各大学の教育の過不足を見出すことができた、など)。 【回答5.】 一番の大きなメリットは、基準が揃って、各施設の指導医がどの医学校の医学生に対しても共通の指導が行いやすくなることです。以前、各施設から評価表が異なると指導しにくいため評価基準を揃えてほしいということでこれが実現しました。大学毎の教育の過不足を見出すことができるというのも大きなメリットです。例えば、本学では、夏に各病院の指導医・事務担当者に向けた実習説明会を開催しているのですが、本学の学生はこういう部分が苦手な傾向があるので、指導の際にご参考になさって下さいと、客観的なグラフの形でわかりやすく提示され、フィードバックされています。 【質問6.】 臨床研修の「たすきコース」では、一年目にプライマリケアを学ぶために学外病院での研修を専攻されるとのことですが、このコースを選択する医師の進路(専攻)を可能な範囲でご教示ください(例、3年目以降は専門系の専攻が多い、など)。 【回答6.】 具体的に「たすきコース」と「エルムコース」の進路の比較は行っておりませんが、研修医の多くは「たすきコース」を選択して市中病院で多くの診療科の研修を経験した後、2年目の大学研修で最終的に専攻を決定している様子です。ただ、研修医(入局予定者)に対し「たすきコース」を推奨し、2年目の自由選択で当該科を長期に選択することで専門研修の一部を開始することが望ましいとしている診療科として皮膚科、精神科があります。 【質問7.】 鹿児島大学病院と連携する広域プログラムはとても興味深いです。これまでの実績についてご教示ください。 【回答7.】 2016年から開始され、両大学で毎年それぞれ2~5名(希望者が毎年不定)の研修医が遠隔地での地域研修を行っております。コロナ禍で2年ほど中断しましたが、2022年度から再開されています。研修医はあらかじめ指定されたいくつかの研修対象施設の中から自由に2箇所を選択し、2ヶ月の地域研修にあてます。本プログラムの研修医評価はきわめて良好であり、鹿児島では種子島の施設、北海道では利尻島の施設の人気が高いようです。 【質問8.】 「国際的医療人育成プログラム」や「CLARCプログラム」の選択者についてもご教示いただけますでしょうか? 【回答8.】 「国際的医療人育成プログラム」は例年1~5名と比較的少人数であり、英語のレッスンなどは全員参加で小クラス形式で実施しています。「CLARCプログラム」は診療科が限定されがちであり、これまで病理診断科専攻者の数名にとどまります。 【質問9.】 CLARCプログラムは、マッチング協議会が設定する「臨床研究医コース」との差別化はどの様に為されるのでしょうか? 【回答9.】 ご質問は、「臨床研究医コース」ではなく、極めてよく似た形式である「基礎研究医プログラム」との相違についてのものと判断いたします。「基礎研究医プログラム」と「CLARCプログラム」は前者が研修2年目の後半6ヶ月を臨床研修から離れて基礎教室での研究にのみ充てるのに対し、後者(CLARCプログラム)は研修2年目から大学院に入学することが条件であり、その後の1年間は日中に通常の臨床研修を行い、17時以降を大学院研究に充てるという立て付けになっています。やはり、「CLARCプログラム」では時間の使い方が難しいことから、大学院研究と臨床研修がほぼ並行して行うことができる病理診断科専攻を決めている研修医にしぼられてしまう状況となっている事実があります。また、最近の働き方改革の動きには合致しない面があり、プログラムの見直しが必要と考えています。 |
| 第15回 滋賀医科大学の記載記事(R4.12.22掲載)への感想・質問 |
|---|
| 1)「ヘルス・ケアシステムの質の向上に貢献するための能力」は、具体的にどのような能力を想定されておられますか? 2)「地域里親による医学生支援プログラム」は興味深い取り組みです。この里親には、地域の方々、医師、他職種の皆様など、どういった方がなるのでしょうか? 3)「滋賀医療人育成協力機構」はどのような事業をされてきたのでしょうか? 4)「地域枠」、一般選抜「地域医療枠」、学校推薦型選抜「地元医療枠」の相違についてご教示下さい。 5)地域医療教育検討専門委員会の具体的な役割をご教示下さい。 6)医学科4年生で学ぶ「社会医学フィールド実習」や「法医学」は具体的にどのような行政機関で行うのでしょうか? 7)行政機関、教育研究拠点病院、医療介護団体との連携で、地域包括ケアシステムを理解するための選択制実習の取り組みが大変興味深く感じました。正課内で全学生が地域包括ケアシステムについて理解するための講義、等をされているか、ご教示ください。されている場合、どの部署が講義を担当されていますか? 8)臨床研修マッチングに先んじて選考される「地域医療重点プログラム」とは、どのようなものでしょうか?地域枠学生だけが応募できるのでしょうか? (新潟大学) |
| 【質問1.】 「ヘルス・ケアシステムの質の向上に貢献するための能力」は、具体的にどのような能力を想定されておられますか? 【回答1.】 ・ 本学が設定している医学部医学科のアウトカムのうち、大項目「F.地域医療への貢献」に分類している以下の5つの小項目は、すべて、将来的に、「ヘルス・ケアシステムの質の向上に貢献するための能力」の基盤になると考えています。 F.地域医療への貢献 1.保険制度をはじめとした医療提供体制(救急医療や在宅医療を含む)について説明できる。 2.保健・医療・福祉・介護の施設間や職種間での連携の必要性とその方法について説明できる。 3.地域医療に積極的に参加できる。 4.地域住民に対する疾病予防、健康増進、安全確保のための活動に積極的に参加できる。 5.災害医療に積極的に参加できる。 【質問2.】 「地域里親による医学生支援プログラム」は興味深い取り組みです。この里親には、地域の方々、医師、他職種の皆様など、どういった方がなるのでしょうか? 【回答2.】 ・ 県内外で活躍されている卒業生や医療従事者が「里親」となり、地域住民の皆さん等には「プチ里親」としてご協力いただいております。 【質問3.】 「滋賀医療人育成協力機構」はどのような事業をされてきたのでしょうか? 【回答3.】 国立大学法人滋賀医科大学および学校法人自治医科大学の学生、滋賀県出身の医学生並びに看護学生、県内看護系育成機関に在学する看護学生に対して、地域医療を担う医療人の育成支援に関する活動を行います。 また、滋賀県民の皆様への医療福祉に関する啓発活動を行います。 これらの活動をとおして、地域の医療を支える医療人を協力して育成することで、滋賀県の医療福祉の向上に貢献します。 (1)地域理解研修活動への支援 滋賀医科大学 里親学生支援室と連携して、夏休み、春休み時期に、地域理解、地域医療者や住民との交流を目的とした宿泊研修を実施します。 (2)医学生を対象とした地域医療夏期ワークショップ支援 滋賀県出身自治医科大学同窓会「さざなみ会」と、地域包括ケアセンターいぶきとの共催で、医学生に対して夏休みに地域医療ワークショップを開催し、地域医療の現状把握を行ないます。 (3)病院・診療所実習等の情報公開 夏期休暇に行われる県下の病院・診療所での実習情報を集め、関係学生に周知します。 (4)地域医療等に関する市民講座の開 地域住民を対象に、医療の最新知識、医療機関の上手な利用方法、がん予防などについて啓発活動を行います。 (5)大学、病院、診療所等職員の学生指導レベル向上のための研修 医学生等への教育・学生支援技術向上のための研修を実施します。 <参考URL:NPO法人滋賀医療人育成協力機構ホームページ> http://www.shiga-iryo-ikusei.jp/index.php 【質問4.】 「地域枠」、一般選抜「地域医療枠」、学校推薦型選抜「地元医療枠」の相違についてご教示下さい。 【回答4.】 【推薦入試「地域枠」:平成10年度~平成23年度】 滋賀県内の高等学校を卒業見込みの者を募集する枠です。 【推薦入試「滋賀県枠」:平成24年度~令和元年度】 滋賀県内の高等学校を卒業見込みの者、または、滋賀県外の高等学校又は中等教育学校を卒業見込みの者で、本人又は1親等の親族のいずれかが、滋賀県内に住所を有する者を募集する枠です。 【一般選抜「地域医療枠」:令和2年度~】 地域医療に強い意欲を持ち、滋賀県が設定する「滋賀県医師養成奨学金」を入学初年度より貸与を受け、卒業後、滋賀県知事が指定する滋賀県内の病院で診療業務に従事するとともに、滋賀県医師キャリアサポートセンターが定めるキャリア形成プログラムに参加する意思を持った者を募集する枠です。 【学校推薦型選抜「地元医療枠」:令和2年度~】 滋賀県出身者のうち、地元医療に強い意欲を持ち、滋賀県が設定する「滋賀県医師養成奨学金」を入学初年度より貸与を受け、卒業後、滋賀県知事が指定する滋賀県内の病院で診療業務に従事するとともに、滋賀県医師キャリアサポートセンターが定めるキャリア形成プログラムに参加する意思を持った者を募集する枠です。 ・滋賀県出身者とは、(1)又は(2)のいずれかに該当する者です。 (1) 滋賀県内の高等学校を令和4年3月に卒業した者又は令和5年3月に卒業見込みの者。 (2) 本人又は父母、祖父母、未成年後見人のいずれかが、新たに入学する年度の4月1日の1年前の日より前から、引き続き滋賀県内に住所を有する者。 【質問5.】 地域医療教育検討専門委員会の具体的な役割をご教示下さい。 【回答5.】 地域医療教育検討専門委員会は、次の各号に掲げる事項を審議します。 (1) 医学科学生の地域医療教育に関する事項 (2) 地域医療教育における学内の他部署との調整に関する事項 (3) 地域医療教育における学外機関や行政との連携及び調整に関する事項 (4) その他学生の地域医療教育に関し必要な事項 【質問6.】 医学科4年生で学ぶ「社会医学フィールド実習」や「法医学」は具体的にどのような行政機関で行うのでしょうか? 【回答6.】 滋賀県庁や保健所、滋賀県警察本部等で実施しています。 【質問7.】 行政機関、教育研究拠点病院、医療介護団体との連携で、地域包括ケアシステムを理解するための選択制実習の取り組みが大変興味深く感じました。正課内で全学生が地域包括ケアシステムについて理解するための講義、等をされているか、ご教示ください。されている場合、どの部署が講義を担当されていますか? 【回答7.】 以下のとおり6年間を通じて地域包括ケアシステムの理解を図っています。 (1年)医学概論Ⅰ・Ⅱ[医学・看護学教育センター] 地域の診療所や中核病院で地域医療に従事する医師や社会福祉協議会の職員を講師に招き、入学早期から地域包括ケアシステムを意識する機会としている。 (2年)地域医療体験実習Ⅰ[医学・看護学教育センター] 滋賀県下を中心に、老人保健施設やケアハウス等が併設されている医療機関において、見学を中心とした1週間の実習を行い、医師のみならず、現場のさまざまな医療職者による指導のもとで、地域の医療・介護・福祉・保健等の実際に触れ、多様な経験を重ねることで、地域における医療の仕組みや役割についての理解を深める。 (4年)公衆衛生学[NCD疫学研究センター] 地域医療・地域保健の在り方と現状及び課題を理解し、地域医療に貢献するための能力を獲得することを目的とした講義を実施する。 (5年)臨床実習(ローテーション)[医学・看護学教育センター] 実習期間中、地域医療教育研究拠点病院における4週間の実習、滋賀県下の診療所における1週間の実習、及び1日間の消防署における救急車同乗実習を実施することにより、地域との連携を意識した臨床実習を行っている。 (6年)学外臨床実習[医学・看護学教育センター] 地域社会で求められる保健・医療・福祉・介護等の活動を通して地域医療と地域包括ケアシステムを一体的に構築することの必要性・重要性を学ぶことを学修目標として、滋賀県下の診療所~中核病院(2カ所)において医療チームの一員として実習を行う。 【質問8.】 臨床研修マッチングに先んじて選考される「地域医療重点プログラム」とは、どのようなものでしょうか?地域枠学生だけが応募できるのでしょうか? 【回答8.】 地域医療重点プログラムは、本院の標準型総合研修コースであるAプログラムに、医師少数スポット※での地域医療研修を組み込んだコースです。 ※ 滋賀県には国が示す指標による「医師少数区域」はありませんが、無医地区および無医地区に準ずる地区や、へき地診療所がある区域が、県によって「医師少数スポット」として設定されています。 2年目ローテートの際に、Aプログラム同様の地域医療研修A(市中の協力施設)4 週間を行う他、医師少数スポットに位置する診療所において 12 週間の地域医療研修Bを行います。 通常の地域医療研修Aでは、県内の各市町村における診療所等において研修を行いますが、医師少数スポットでの地域医療研修Bでは、県内の過疎地域において、その地域の特性に応じた診療活動を経験します。地域医療研修Bの研修先である診療所は、「地域包括ケアシステムの担い手」として、地域住民の健康管理に加えて、看取りや他院への紹介等を行っており、研修医は生のへき地医療を経験することが可能です。 特にへき地において、高度急性期の医療が必要となった際には、中核病院への紹介も重要な役割です。高齢者が多く、交通手段が限られるへき地では、市街地よりも患者やその家族の目線に立って紹介先を検討する必要があります。実際の事例から指導医と討論し考察を深めることにより、へき地における患者や家族の立場を考えた診療を実際に経験することができます。 将来県内の医療機関に勤務し医療活動を行う上で、県内の地域医療の実態を認識し、実践する能力を修得することが可能となるプログラムです。 なお、マッチングに先んじての採用は地域に従事要件のある地域枠学生のみですが、募集定員が埋まらなかった場合に限り、マッチング及び二次募集等で一般学生の応募も可能です。 |
| 9)興味深く拝読させて頂きました。特に「里親学生支援室」と「滋賀医療人育成協力機構」に関して、良い制度と思いました。このため、この2つについてもう少し詳しくご紹介いただければ幸いです。「里親学生支援室」の組織は、医学部内にあるのでしょうか。この組織は、具体的にどのような構成になっており、どの様な支援をされているのか、ここで言う「里親」の意味とは何か、学生と1対1関係にあるのでしょうか、などを教えて下さい。次に「滋賀医療人育成協力機構」ですが、NPO法人とのことですが、どの様な方が関与しているのでしょうか。この組織の具体的な活動についても教えて頂けると有難いです。これらのことが分かると、同じく学生の地域定着を目指している我々にとっても非常に参考になります。宜しくお願い致します。 (弘前大学) |
| 【回答9.】 【里親学生支援室】 「里親学生支援室」は、本学医学・看護学教育センター学生生活支援部門の下に設置しております。 組織の構成は、室長、室員9名、学外室員3名及び事務局2名となっており、本学教職員が兼務しております。 また、「里親」という名称ですが、県内で活躍されている医療従事者や地域住民の皆さんが自分たちがほしいと思う医師・看護師を、本学といっしょに、親身になって時間をかけて育てていきたいという思いをこめて「里親」と名付けております。 里親事業には「里親」と「プチ里親」があり、「里親」は、将来滋賀県内で働くことに興味を持っている本学の新入生に対して、県下で活躍する一先輩として、日々の学習、クラブ活動などの学生生活や、将来の進路などの相談にのるアドバイザーで、「プチ里親」は、県下で生活する住民の立場から、地域の歴史や文化、産業や生活、医療の大切さなどを直接学生に伝えるアドバイザーです。 また、学生1名に対して、「里親」1名となっています。 <参考URL:地域「里親」による学生支援ホームページ> http://www.shiga-med.ac.jp/~satooya/ 【滋賀医療人育成協力機構】 滋賀県や県内の市町、病院、診療所、医師会、看護協会及び地域の皆さん等、様々な方々にご協力いただいております。具体的な活動については、質問3をご覧ください。 |
| 10)1、2学年 選択科目「全人的医療体験学習」とあるが、医学部で選択科目を設定することは難しい。どのように工夫されているのか。また、他の選択肢としてどのような科目を用意されているのか。 11)「滋賀県医師キャリア形成卒前支援プラン」について、具体的な講義・実習など(そして資金援助等あれば)教えてほしい。 (岐阜大学) |
| 【質問10.】 1、2学年 選択科目「全人的医療体験学習」とあるが、医学部で選択科目を設定することは難しい。どのように工夫されているのか。また、他の選択肢としてどのような科目を用意されているのか。 【回答10.】 本学医学部医学科では、教養科目(選択)を2年間で12単位修得することを卒業要件の一部としており、「全人的医療体験学習」はそれらの選択科目の1つとして開講しています。 なお、一般選抜の「地域医療枠」及び学校推薦型選抜の「地元医療枠」で入学した学生(=地域医療重点コースの学生)については、「全人的医療体験学習」を必ず選択するよう履修指導を行っています。 また、その他の選択科目は、哲学、文学、芸術学や法学といった一般教養科目となっております。一般教養科目に関する工夫としましては、滋賀県内の他大学とも連携し、他大学開講の科目も選択可能とし、できるだけ幅広い分野から選択できるようにしております。 【質問11.】 「滋賀県医師キャリア形成卒前支援プラン」について、具体的な講義・実習など(そして資金援助等あれば)教えてほしい。 【回答11.】 【プランの内容】 (1)滋賀県医師キャリアサポートセンター懇談会 滋賀県で活躍する先輩医師が講師となり、これまでのキャリアや滋賀県で働く魅力について講演を行います。 (2)「学内で地域医療の体験ができる」課外授業シリーズ 地域で活躍する医師を講師に招き、地域医療医師として必要なスキルや知識を実践的な内容で地域医療を志す医学生等に向けて講義を行います。 (3)滋賀県の医療と歴史・文化を学ぶ「宿泊研修」 滋賀県の医療と歴史・文化を学ぶ一泊二日の宿泊研修を行い、地域の医療機関に勤務する医師や看護師、地元の住民の方と直接交流する機会を設けます。 (4)自治医科大学・地域枠学生の夏季地域医療実習 自治医科大学滋賀県同窓会(さざなみ会)と共同で、地域医療を第一線の現場で体験すること、地域医療に対する動機を明確にすること、将来地域医療に従事する仲間との交流を深めることを目的に地域医療実習を行います。 ※ なお、本プランの参加は原則無料ですが、プランによっては参加費や交通費が自己負担となる場合もあります。また、本プランは毎年、対象学生に意見聴取を行い、滋賀県地域医療対策協議会において協議のうえ更新します。 |
| 第14回 千葉大学の掲載記事(R4.11.22掲載)への感想・質問 |
|---|
| 1)地域医療教育学講座の【地域で診療する能力につながる講義や実習】について、具体例をご提示いただけますでしょうか 2)地域医療教育学講座でマネージされている臨床実習は、医学教育学講座が統括される診療参加型実習の一部でしょうか、あるいは希望者が夏季休暇等に参加する実習でしょうか。 3)6年一貫の地域医療学修の年次進行について具体的にお示しいただけますか。 4)医学生同士の連携強化による診療・指導基盤の構築、多職種連携能力とリーダーシップを高める取り組みとは、具体的にはどのようなものでしょうか。 5)地域病院アテンディングの先生方に対する教育(FD)はどういった内容に焦点をあてていますか。 6)千葉大学における地域枠の定員をお示しください。 (新潟大学) |
| 【質問1.】 地域医療教育学講座の【地域で診療する能力につながる講義や実習】について、具体例をご提示いただけますでしょうか。 【回答1.】 ・ 医学部早期(1年次)の段階から総合診療医や地域病院で活躍する医師によるケーススタディを基盤とした授業を行っています。高度な医学的知識、疾患に偏らず、プライマリケア、患者の社会的背景、地域包括ケアシステム、医療資源の活用など地域医療の実践を重視した題材で学年に応じたレベルの課題を作成し、スモールグループディスカッションで学生自らの課題解決策の検討、提案を引き出すようにしています。 ・ 医学部1、2年次の地域病院実習では、学生が地域病院アテンディングの在籍する病院に出向き、外来、病棟、訪問診療の現場に同席、患者・地域住民とのコミュニケーション、多職種とのコミュニケーション、バイタルサイン測定やPPE装着など初歩的な臨床技能を体験します。地域病院アテンディングは事前に授業で自身の医療現場やキャリアをプレゼンテーションし、事前課題の提示や実習打ち合わせを直接行っています。学生が地域病院で活躍する医師を身近な存在と捉え、ロールモデルから学び自身のキャリア形成に活かすことを可能とします。 【質問2.】 地域医療教育学講座でマネージされている臨床実習は、医学教育学講座が統括される診療参加型実習の一部でしょうか、あるいは希望者が夏季休暇等に参加する実習でしょうか。 【回答2.】 ・ 医学教育学講座が統括する診療参加型臨床実習の一部です。必修期間および選択期間のどちらでも実習が可能です。 【質問3.】 6年一貫の地域医療学修の年次進行について具体的にお示しいただけますか。 【回答3.】 6年一貫の地域医療学修ですが、以下の学年での履修を計画しております。 1.地域医療学:1?4年次 1?2年次:地域医療学講義を行う。 3年次:地域志向型PBLを行う。 4年次:地域志向型PBL、地域志向型シミュレーション教育を行う。 早期地域医療体験:1?4年次 1?2年次:早期地域体験実習を行う。 3年次:医師見習い体験を行う。 1?4年次:サービス・ラーニングを行う。 3. 地域IPE:1?6年次 1年次:地域IPE Step1「共生」を行う。 2年次:地域IPE Step2「創造」を行う。 3年次:地域IPE Step3「解決」を行う。 4年次:地域IPE Step4「統合」を行う。 5?6年次:地域IPE(クリニカルIPE)を行う。 4.ジェネラリスト入門:1?4年 1?2年次:ジェネラリスト入門講義を行う。 3年次:ジェネラリスト入門講義、ジェネラリスト育成PBLを行う。 4年次:ジェネラリスト入門講義、ジェネラリスト育成PBL、ジェネラリスト育成シミュレーション教育を行う。 5.統合的クリニカル・クラークシップ:4?6年次 4?5年次:臨床実習Ⅰ(コア・クリニカル・クラークシップ)を行う。 5?6年次:臨床実習Ⅱ(アドバンスト・クリニカル・クラークシップ)を行う。 4?6年次:統合型遠隔カンファレンスを行う。 6.地域クリニカル・クラークシップ:5?6年次 5?6年次:地域医療実習、アスパイアプロジェクトを行う。 低学年から臨床実習前教育として、地域医療学、早期地域体験、ジェネラリスト入門を展開し、統合型および地域クリニカル・クラークシップでは、臨床現場でこれまで培った能力を実践的な能力へ昇華させるプログラムとしています。 【質問4.】 医学生同士の連携強化による診療・指導基盤の構築、多職種連携能力とリーダーシップを高める取り組みとは、具体的にはどのようなものでしょうか。 【回答4.】 千葉大学では、多職種連携能力とリーダーシップを高める取組として、多年次積み上げ式のIPEプログラム(亥鼻IPE)を行なっています。さらにそのプログラムを発展させ、クリニカルIPEへと継続的に専門職連携教育を涵養し、地域医療の場で活躍できる能力を獲得するプログラムを実装する予定です。また、実際の医療現場体験を通じた学習、医薬看等の複数の学部混成メンバーによるグループワーク、さらにはリフレクションとポートフォリオによる振り返りによる学習を行うことで上記能力の開発を行います。 【質問5.】 地域病院アテンディングの先生方に対する教育(FD)はどういった内容に焦点をあてていますか。 【回答5.】 ・ 地域医療現場に則したアウトカム基盤型医学教育,指導方略,学修者評価等の理論、考え方を共有化し、地域病院に おけるアテンディング自身の医学部生実習、研修医教育を題材としたプログラム開発、指導方法のスキルアップに焦点を当てています。FD実施内容例を以下に示します。 -1 地域病院指導医に必要な資質・能力 -2 地域枠学生の授業、実習に関するプログラムデザイン、目標設定 -3 学修者評価:総括評価・形成的評価・信頼性妥 当性・観察評価ツール -4 学修?実習方略:WBL(Workplace Based Learning)?フィードバックの実践 -5 マイクロティーチング(模擬授業・模擬実習)の理論と実践 -6 ICTを活用した授業・実習 -7 授業評価 -8 メンタリング・メンターの役割、キャリアサポート -9 教育プログラム評価とIR(カリキュラム/プログラム評価) -10 医学教育の最近の潮流 【質問6】 千葉大学における地域枠の定員をお示しください。 【回答6.】 恒常的な定員が5名で、2022年度現在、国及び千葉県の医師確保対策の計画等によって、20名まで増員されています。 |
| 7)2ページ目の「県内における地域医療教育ネットワークの構築・強化」について大学病院と地域の病院、地域の病院同士、総論は賛成だと思いますが、それぞれの利害関係が複雑だと思います。 皆がウインウインになるようにどのような工夫をしておられるのか教えていただきたいです。 (岐阜大学) |
| 【回答7】 ・ 地域医療教育の重要性は、近年国内外からの報告により、多様なプログラムとキャリア選択への有効性が示されています。医学部カリキュラムにおける地域の授業、実習では、地域病院指導医の指導力が多大な影響を及ぼすことになります。しかし、地域病院で活躍する医師のキャリア形成の中で医療現場に即した指導方法を学ぶ機会は少なく、教育実践に苦心している現状があります。 ・ 大学の医学教育部門(医学教育学講座および千葉県寄附講座地域医療教育学講座)が、地域医療を教育の場とした医学部授業・実習、臨床研修のカリキュラムを作成、地域病院指導医(地域病院アテンディング)を対象にFDを介した各病院でのプログラム開発、指導方法のスキルアップなどの指導医育成を担当します。 ・ 地域病院アテンディングは大学の医学教育部門と連携し、定期的なFDに参加することにより、学修者(医学部生、研修医など)のニーズ、学修アウトカムを明確に認識します。その上で、自身の地域医療現場の特性を活かした実習・研修プログラム作成、指導方法を、診療を大きく妨げることなく、効率的に修得することが可能となっています。大学や地域病院同士でコミュニティが形成され、臨床指導に関する相談や改善がしやすくなっており、地域病院アテンディング自身の指導の質の向上を可能とします。 ・ 地域病院アテンディングの活動により、他の指導医、多職種へ影響が及び、地域病院全体の臨床教育文化、教育の質が変化してきています。(地域病院アテンディング、地域教育病院は県の協力により年次的に増やす計画です。)学生、研修医、専攻医が地域で学修する機会、質ともに高い教育、研修を受けることが可能となれば、興味がより一層地域に向くことになります。将来的な地域での研修、医療実践、定着が見込まれ、地域の医師偏在解消に貢献、医療の質が向上する可能性が高まります。これらのアウトカムは短期的、長期的なモニタリングが必要であり、県、大学、地域病院が共同し検証を開始しています。 |
| 第13回 秋田大学の掲載記事(R4.10.25掲載)への感想・質問 |
|---|
| 1)6年間の一貫教育で、低学年時にどのような学外教育者が関わっておられるでしょうか? 2)シミュレーション教育センターの機器の維持・管理、使用予約、指導等はどのようにされていますでしょうか? 3)現時点で取り組んでいるデジタル教育の具体的内容をご教示ください。放射線診断、病理診断、超音波診断の他に、実際の診療をオンラインで行う試みはされているのでしょうか? (新潟大学) |
| 【質問1.】 6年間の一貫教育で、低学年時にどのような学外教育者が関わっておられるでしょうか? 【回答1.】 1、2年次は以下の状況になります。 [1年次] 1.医療面接・臨床推論関連 ①日本語医療面接模擬患者さん -(胸痛・腹痛、日本語医療面接OSCE時) ②英語医療面接指導教員とネーティブ英語模擬患者さん - (胸痛・腹痛、英語医療面接OSCE 時) 2.早期臨床実習(2学期)関連 ①県内教育連携医療機関の医師 -(2学期の早期臨床実習先13か所:以前は卒業時PCC-OSCEに 来ていただいておりました。) 3.プロフェッショナリズム・医療行動科学関連講義 ①県内研修病院指導医―(1年生のための医師・医学生のプロフェッショナリズム講義) ②秋田県立リハビリテーション・精神医療センター医師(音声言語以外の言語について知ろう) ③元WHO医師: 国際医療について・ワクチンについて ④米国ホスピタリスト:米国のコロナ事情と医師のキャリア ⑤某企業産業医(元教員)-(マナー講義) [2年次] 1. チーム医療・医療連携、地域包括ケア関連 ①在宅診療を行う『診療所医師』、『訪問看護・看護師』、『薬剤師』、『ケアマネージャー』 (多職種連携教育・地域包括ケア・医療連携・在宅医療PBL) ②診療所医師(地域包括ケア、終末期医療、ACP、死生観、ナラティブブックについて) 2.キャリア教育関連 ①他大学の女性教員2名(医師の男女共同参画・ダイバーシティー・アンコンシャスバイアス・ キャリアサポートPBL) 【質問2.】 シミュレーション教育センターの機器の維持・管理、使用予約、指導等はどのようにされていますでしょうか? 【回答2.】 ・ シミュレーション教育センター1階事務室に附属病院の総合臨床教育研修センターとあきた医師総合支援センター(地域医療センター)職員が常駐し、共同して運用しています。主担当は、予約等の管理職員と2016年度からはシミュレーション機器のスペシャリストとして臨床工学技士が1名常駐しており、全機器のメンテナンスや教育・研修のサポートを行っています。 ・ 機器の維持経費は、病院および一般財団法人本道医学振興会(http://www.med.akita-u.ac.jp/hondo/)、関連病院協議会から捻出していますが、修理や購入は高額であり常に課題となっています。 ・ 指導に関して:将来のニーズを見越して、2012年シミュレーションセンター開設当初から、総合臨床教育研修センターの構成コアメンバー(医師3名・看護師3名等)は、ハワイ大学SIMTIKシミュレーションセンターのバーグ教授のセミナー(Fun Sim J)等でシミュレーション教育を学び、学内の興味ある医師や看護師チーム、多職種連携的に普及してきています。現在、臨床参加型臨床実習のうち11の診療科で学生指導にもシミュレーション教育を導入して経験保証を進めています。 ・ 東北シミュレーション医学・医療教育研究会(https://www.csl.med.tohoku.ac.jp/TWSE/index.html)は、身近な取り組みの発表・共有現場として2013年に設立され、各機関におけるシミュレーション教育の普及に役立っています。 【質問3.】 現時点で取り組んでいるデジタル教育の具体的内容をご教示ください。放射線診断、病理診断、超音波診断の他に、実際の診療をオンラインで行う試みはされているのでしょうか? 【回答3.】 ・ 2010年より、各講座統一したデジタル教育のためにデーターパシフィック社製のウエブクラスを医学部で導入しました。2016年より、大学内、基礎教養教育から専門教育まで、ウエブクラスに統一となりました。これにより、全学科が6年間一貫してデジタル教育を進める体制となっておりました。その後、コロナ感染症対応で使用頻度が増えましたが、学内統一していたので比較的対応することができました。 ・ ウエブクラスを利用した資料配布、動画配信、チェックテスト機能など各種デジタル活用を普及するために、2015年より本講座でFDを実施し普及活動を実施しました。2019年度の年間の利用が全学で650科目のコース(ほどんどが医学部のコース)で進めておりました。その後、コロナ後には10倍の6000科目のコースとなっております。 ・ 医学部の方では、それまでの基盤がありましたので、講義・演習・実習における資料や動画の配信+自己評価としてのチェックテストなど、各講座工夫したデジタル活用が進み、それを基盤に対面の講義・演習(シミュレーション教育)・実習をよりアクティブ化する方向となってきました。 ・ 他に、講義では、オンライン化による海外も含めた講師の多様化、オンラインによる1年次英語医療面接OSCE、症例ベースのシミュレーションセミナーのオンライン配信によるオープン化などです。(参考;医学教育サイバーシンポジウム https://vimeo.com/437425837) |
| 1)1年生の初年次ゼミ~医療行動科学は、魅力的なそして先進的な取り組みだと思いますが、学生・教員のアンケート(満足度調査)などのデータがあれば教えていただけますでしょうか。1年生から臨床系の教員に参画してもらうことに対する、負担増などの懸念が危惧されますが、どのように対応しておられるのでしょうか。 (岐阜大学) |
| 【回答1.】 ・ 入学直後の1年生の初年次ゼミ~医療行動科学は、最も重視しております。その中で、9月末の看護演習・実習は、附属病院看護部と保健学科の皆さんに、10月11月の早期臨床実習では、各診療科や県内医療機関の指導医の皆さんにお世話になります。 ・ 一方、その他のほとんどのコマを占める講義・演習・OSCE部分は、医学教育学講座が担当しております。その際、7月と12月に行う日本語・英語OSCE、心エコー・腹部エコー・肺の聴診OSCEも、全自動アナウンスと録画による評価で、講座単独で実施しております。したがって、各講座の先生には、早期臨床実習以外は、ほとんどご負担をかけずに進めております。 ・ 授業評価について、1年生の初年次ゼミ~医療行動科学は、毎年、学生からの授業評価でも高く評価をうけることができております。実習中の5,6年生の学生に聞くと、『1年生の時に、胸痛・腹痛の臨床推論・医療面接の講義・演習・OSCEで、各科横断的縦断的な水平・垂直統合教育の学びを経験することで、その後の基礎医学、臨床医学、医療行動科学、臨床医学の各専門分野を学ぶときにも、無意識のうちに症候ベースのところに結びつけていると思う。臨床実習中の臨床推論はなかなか難しいが、もし1年次通年の経験がなかったら、実習中にもっと苦労していると思う。』と言った意見をいただいております。 ・ このように重要な1年次の講義は、たくさんの講座がかかわるアラカルト形式ではなく、一定のメンバーで学年を超えた統合教育を意識した展開が重要と考えられます。 |
| 第12回 大阪大学の掲載記事(R4.9.26掲載)への感想・質問 |
|---|
|
1)診療参加型臨床実習が合計で44週とのことですが、臨床実習は全体でどの程度行っているのでしょうか? |
| 【質問1.】 診療参加型臨床実習が合計で44週とのことですが、臨床実習は全体でどの程度行っているのでしょうか? 【回答1.】 早期臨床体験実習を合わせて69週です。 【質問2.】 各診療科が、大学病院の高度先進医療と関連病院でのcommon diseaseをバランスよく経験できる実習の構成を工夫、とありますが、一連の実習で行うのでしょうか?診療科ごとの構成の実例をいくつかお示しいただけると参考になります。 【回答2.】 診療参加型臨床実習は4週間ごとのローテーションで、附属病院と関連病院のバランスは、各診療科に任せています。たとえば、消化器外科であれば2週間を附属病院、残り2週間を関連病院で実習します。消化器内科であれば3週間を附属病院、残り1週間を関連病院で実習します。 【質問3.】 医学生の臨床実習到達目標をEPOCを参考にしたシステムで行っているとのことですが、この卒前情報は卒後大阪大学附属病院で臨床研修を行う際にも利用されているのでしょうか? 【回答3.】 現時点では利用しておりませんが、今後は利用したいと考えております。 |
| 1)研究教育調査室(IR)の「到達目標の達成段階」に関して具体的な解析をお聞きしたいです。 (島根大学) |
| 【質問1.】 研究教育調査室(IR)の「到達目標の達成段階」に関して具体的な解析をお聞きしたいです。 【回答1.】 臨床実習の途中(5年次夏休み)と終了(6年次10月)の2段階で回収し、それをIRで集計することで、到達目標を段階的に達成していることを確認しています。 |
| 第11回 東京大学の掲載記事(R4.8.26掲載)への感想・質問 |
|---|
| 1)地域医療構想における4病床機能と在宅医療を学生が満遍なく学修できるようにしているとのことですが、回復期や慢性期の病床を経験する機会について教えてください。 2)地域医療のICT化を視野に入れたICTを活用した診療参加型実習の開発について、具体例がありましたらお教えください。 3)これまでに他県の僻地医療拠点での研修の後、当該研修地域での専門研修を行ったという事例はあったでしょうか? (新潟大学) |
|
【質問1.】 |
| 1)多職種連携教育は、とても有意義だと考えます。かなりの回数を実施しないと単位化は難しいと思いますが、どのように工夫されているのでしょうか。 2)オンライン診療を含めてICTの活用に積極的に取り組んでおられます。どうしても見学型実習になりがちではないかと懸念されますが、どのように診療参加型実習を目指されるのかご教示ください。 (岐阜大学) |
| 【質問1.】 多職種連携教育は、とても有意義だと考えます。かなりの回数を実施しないと単位化は難しいと思いますが、どのように工夫されているのでしょうか。 【回答1.】 本学は2年生の秋に医学科進学者が内定し、その時点から医学科の授業が開始されるため、限られた時間で数多くの事を学ぶ必要に迫られております。 そのため、多職種連携教育については単独の科目としては実施しておらず、2年生については「チュートリアル」、4年生については「臨床導入実習」という科目の一部として実施しております。 回数としては必ずしも多いとは言えませんが、その分内容や運営について工夫をするようにし、多職種連携教育の重要性やポイントについて学生が修得できるよう留意しております。学生からは、印象的であったというコメントを得ています。 【質問2.】 オンライン診療を含めてICTの活用に積極的に取り組んでおられます。どうしても見学型実習になりがちではないかと懸念されますが、どのように診療参加型実習を目指されるのかご教示ください。 【回答2.】 担当の指導教員と相談し、単なる見学にならないよう、なるべく双方向性を持たせ、アクティブラーニングになるようにしております。オンラインのもと、実際の身体所見、画像所見、検査所見などから臨床推論や治療方針の立案を行う、などが主な内容となります。 |
| 1)4病床機能の相互連携の具体例(地域・高齢化率・医療資源等)を教えて下さい。 2)「僻地医療拠点病院」における地域医療研修を行う研修医数(拠点毎)を教えて下さい。 (島根大学) |
| 【質問1.】 4病床機能の相互連携の具体例(地域・高齢化率・医療資源等)を教えて下さい。 【回答1.】 地域は、当院周辺の地区(23区内東部・北部など)が主な連携地域となります。高齢化率については、30%以上と推定しております。実習施設としては、診療所、訪問看護ステーション、居宅介護支援事業所等にご協力いただいております。 【質問2.】 「僻地医療拠点病院」における地域医療研修を行う研修医数(拠点毎)を教えて下さい。 【回答2.】 2022年度の実績と予定を以下に示します。 秋田県 男鹿みなと市民病院 3名 新潟県 佐渡総合病院 2名 新潟県立津川病院 6名 石川県 珠洲市総合病院 2名 輪島市立輪島病院 2名 公立宇出津総合病院 2名 公立穴水総合病院 6名 高知県 大月病院 1名 長崎県 青洲会病院 5名 |
| 第10回 京都大学の掲載記事(R4.7.25掲載)への感想・質問 |
|---|
| 1)京都大学を卒業後に府内で臨床研修を開始する卒業生の割合はどの程度でしょうか。 2)地域医療ビジョンで府立医科大学と協力・連携する場合、どのような部署が窓口となって具体的内容を調整するのでしょうか。 3)京都大学と京都府立医大 、それぞれの役割分担といったものがあるのでしょうか。 (新潟大学) |
| 【質問1.】 京都大学を卒業後に府内で臨床研修を開始する卒業生の割合はどの程度でしょうか。 【回答1.】 卒業年度によって人数に変動はあるのですが、京都大学医学部卒業生のうち、京都府内の臨床研修プログラムに所属する卒業生が約2割~3割程度です。また、臨床研修修了後に大学院生として本学に戻ってくる学生としては、年度により変動はあり、帰学のタイミングにもバラつきはあるのですが、約6~7割程度です。卒後5~7年目に大学院に戻る卒業生が最も多いです。 【質問2.】 地域医療ビジョンで府立医科大学と協力・連携する場合、どのような部署が窓口となって具体的内容を調整するのでしょうか。 【回答2.】 地域医療連携業務については、京都大学医学部附属病院の地域ネットワーク医療部および地域医療連携室が窓口となって具体的内容を担当しています。 https://www.kuhp.kyoto-u.ac.jp/department/management/cncm-cno.html(地域ネットワーク医療部ホームページアドレス) 【質問3.】 京都大学と京都府立医大 、それぞれの役割分担といったものがあるのでしょうか。 【回答3.】 京都市域地域医療構想調整会議では、京都大学医学部附属病院は、特定機能病院として質の高い医療を全国の患者に提供することを理念とし、全ての病床を高度急性期としています。高度急性期医療を提供するべく、二次医療圏以外からの重症患者受け入れに関しても積極的に役割を担っています。また、質の高い医療を提供するために、臨床研究中核病院として新しい医療の研究・開発を担い、iPS細胞等の医療への応用を目指しています。 京都府立医科大学附属病院では、病床機能区分では高度急性期機能を中心に高度医療を提供されています。特定機能病院として、高度で重症度の高い患者診療に集中できるよう、新たな地域医療連携の枠組みによる地域の基幹病院としての役割を果たされています。 これら2つの大学病院では、上記の様なそれぞれの特徴を活かしながら、地域医療構想における地域医療機関との連携のなかで大学病院に求められる役割を分担し、協力して推進しています。 |
| 第9回 山口大学の掲載記事(R4.6.24掲載)への感想・質問 |
|---|
|
1) 地域医療実習の満足度は年々高くなってきているようですが、どの様な工夫をされているのでしょうか? |
| 【質問1.】 地域医療実習の満足度は年々高くなってきているようですが、どの様な工夫をされているのでしょうか? 【回答1.】 実習前に、学生に対し実習の意義や注意点などを詳細かつ丁寧に説明しています。また指導医向け説明会を毎年開催し(近年はWeb)、指導医側の理解と協力を得るようにしています。実習期間中は、教員ができるだけ全施設を巡回するように努力しており、指導医、実習生、担当教員での対話を重ねています。 【質問2.】 山口県の医師不足改善のためには、山口県出身の医学部進学者数が増えることが重要と思いますが、その点についてはどのような状況でしょうか? 【回答2.】 地域枠(修学資金貸与なし)や特別枠(緊急医師確保対策枠と地域医療再生枠:修学資金貸与あり)の入学定員について随時検討を重ねています。 また、山口県出身で医師を志す高校生への働きかけとして、主に県内の高校を中心に、教員が現地に出向き、入試要項、キャリア形成などの説明会を開催しています。 それ以外にも山口県の中高校生を対象にした医師体験実習を山口県医師会と協働で開催し、「医学部を目指すなら山口大へ」という機運を盛り上げています。 【質問3.】 4年次からの臨床実習における地域医療機関での実習と6年次の地域医療実習の違いはどのような点でしょうか? 【回答3.】 前者では、該当診療科で2週間のローテート実習のうちの1日を使い、その診療科の関連病院で学外実習を行うものです。後者は、学生が希望した診療部門のクリニックや地域病院で、1週間の学外実習を行うものです。ローテート実習と選択実習、実習期間、最終学年となり実習内容がより実践的であることなどが相違点となります。 これら以外にも5年次3学期からの臨床実習(選択制、6週間×4診療科)では県内の臨床修練研修指定病院へ積極的に学生を派遣しています。 【質問4.】 図3のアンケート結果は6年生からの回答でしょうか? この結果と山口県内での臨床研修医数の変動との関連はいかがでしょうか? 【回答4.】 6年生からの回答です。アンケートで好意的な回答が増加し、また山口県内の臨床研修医数も増加傾向にありますが、これらの直接の関連性については分かりかねます。 【質問5.】 地域医療実習のどのような部分が満足で、あるいはどのような点が今後の改善課題でしょうか? 【回答5.】 プライマリー領域の様々な症例や手技を経験できることや、往診、地域保険など大学病院や基幹病院とは異なる経験ができることが満足なところとしてよくあげられます。また、熱心な指導医からの説明やディスカッションも学生には好意的です。 一方、忙しいクリニックでは十分な指導時間が確保できないこと、実習時期によっては都合が悪い施設もあること、指導医から見てまだ学生の技能が満足なレベルに達していない場合があることなどが今後の改善課題と考えています。 |
| 第8回 三重大学の掲載記事(R4.5.24掲載)への感想・質問 |
|---|
|
・地域枠Bの倍率はどのくらいでしょうか? また医学部が指定する医師不足地域から地域枠B以外で入学する方はどの程度いるのでしょうか? |
| 【質問1.】 地域枠Bの倍率はどのくらいでしょうか? また医学部が指定する医師不足地域から地域枠B以外で入学する方はどの程度いるのでしょうか? 【回答1.】 大学が指定する医師不足地域には、15市町村(うち2市については、それぞれの市の地域を限定)が含まれます。毎年度の地域枠B入試では、各市町村が推薦できる志願者数を2名以内としていますので、最大でも30名ということになります。しかし、18歳人口が非常に減少している市町村ですので、毎年、それぞれの市町村に被推薦者がいる状況ではありません。過去3年間の志願者数は14-17名でした(2.3-3.0倍)。そのうち大学入試センター試験/大学入学共通テストの結果に基づく第一次選考後に第二次選考の対象になった志願者数は8-10名(第二次選考倍率1.3-2.0倍)でした。過去3年間に全県対象の地域Aあるいは一般入試で入学した地域B指定地域の出身者は、4-5名でした。 【質問2.】 地域枠Aと地域枠Bとの学力差は問題ないでしょうか? 【回答2.】 進級率と医師国家試験合格率に差はありません。地域枠と一般入試(推薦、前期日程、後期日程)との間にも上記の指標に差はありません。むしろ地域枠Bの方が国家試験合格率は良好です。その理由の一つとして、誠実な学習態度があると考えています。実際の授業での成績分布では、地域枠B学生の成績は、上位から下位まで広く分布しています。しかし、留年、国家試験不合格となる最下位層はいないという状況です。1学年5名の地域枠B学生が、下位に集中することはありません。上位5名以内に入り、卒業時に学長表彰を受けた学生もいます。入学者選抜において、地域AとBとの成績に大きな乖離がないように一定の配慮をしています。従って、年度によっては5名の地域枠B学生をとれないこともあります。このことも学力差がない一因かもしれません。 【質問3.】 県外出身者を地域枠等に募集する可能性はいかがでしょうか? 【回答3.】 本学の場合、推薦入試である地域枠A(定員25名)、B(定員5名)以外に、前期日程75名のうち5名を三重県地域医療枠として受け入れており、この地域枠には県外者も応募できます。過去3年間の県外からの入学者数は1-2名です。多様な学生を受け入れるという観点から県外からも一定数の地域枠学生を受け入れるべきであると考えています。 【質問4.】 地域基盤型保健医療教育には県庁がかなり関わっているとのことですが、学内で関わっている組織、スタッフを教えてください。また実際に実践される地域貢献活動にはどのようなものがあるか教えてください。 【回答4.】 授業実施の主体となるのは、医学部医学・看護学教育センターです。センターには、教授1、准教授2、講師1が配置されています。さらに、8名の教育助教(医学科6、看護学科2)を三重県市町村振興協会からの交付金により雇用しています。これらの教育センター教員が本授業を担当しています。また、県・市町村からの寄付講座を持っている総合診療部の教員も4-5名程度協力しています。また、三重県市町村振興協会交付金から2名の授業担当事務補佐員を雇用しています。三重県庁は、主に市町村保健部門との連絡調整を担当してくれています。この授業の実施や地域枠学生の指導などについて連携するため、医学部、三重県庁、三重県市町村振興協会の3者で月例の連絡会を開催しています。 学生による地域貢献活動としては、自治会単位での健康教室(テーマとしては、生活習慣予防、認知症対策、ロコモ予防など)、地元食材を活用した栄養改善活動、保健師活動の補助としてのがん検診受診促進パンフレットの作成、学校・幼稚園での食育、若い母親を対象にした乳幼児の一次救急蘇生講習会などです。 【質問5.】 県内研修医増には地域枠の増員が直結していると思いますが、一方で、臨床研修の改善等による県外流出の減少という要因についてはいかがでしょうか? 【回答5.】 臨床研修の充実が、県内研修医数の増加に寄与していると思います。特に、県内の全ての研修病院が、NPO法人MMC(Mie Medical Complex)卒後臨床研修センターを組織し、県内での研修のフレキシビリティを高めるプログラムを導入したことなどが有効に作用したと考えています。 【質問6.】 卒後も教育センターがキャリア支援に係ることのできる体制は素晴らしいと感じます。当然業務量が増えますが、センターの体制(人数、職種、財源など)をお教えいただけますか? 【回答6.】 人員は上述の通りです。地域医療教育/地域枠学生指導の財源は三重県市町村振興協会からの交付金を活用しています。業務量についてですが、教育センターの活動の対象は学部学生が中心です。学生、初期臨床研修医、専門研修医の指導は、教育センター、附属病院臨床研修キャリア支援部、三重県地域医療支援センター、MMC卒後臨床研修センターの4者が協力して担当していますが、主たる担当部門は徐々に移行していきます。 【質問7.】 初期臨床研修から専門研修に移行する段階で2割程度の流出があるとのことですが、これについて何らかの手立ては講じておられるのでしょうか? 【回答7.】 三重県内で初期臨床研修を行う研修医の80%以上は大学病院以外を選択しています。一方、三重県内の専門研修プログラムの多くは大学病院のプログラムです。そのため、大学病院以外で初期臨床研修中の研修医に対する専門研修プログラムの周知や同プログラムへの誘導が重要である考えています。関連病院長会議やMMC卒後臨床研修センターの活動の中で、初期臨床研修医へのアプローチを強化しています。最も重要なことは、魅力ある専門研修プログラムの提示と指導体制の充実であると考えています。専門研修プログラムの継続的な改善に取り組んでいます。 |
| 第7回 神戸大学の掲載記事(R4.4.25掲載)への感想・質問 |
|---|
|
・1年次のIPW、2年次の福祉施設、3年次の特別支援学校や福祉施設、4年次の在宅ケアなど体系立てた実習は素晴らしいと思います。実際にどの程度の時間数で、どのように実施しているかをお示しいただけるとありがたいです。 |
| 【神戸大学からの回答】 【質問1.】 1年次のIPW、2年次の福祉施設、3年次の特別支援学校や福祉施設、4年次の在宅ケアなど体系立てた実習は素晴らしいと思います。実際にどの程度の時間数で、どのように実施しているかをお示しいただけるとありがたいです。 【回答1.】 時間数については、以下の通りです。いずれもオリエンテーションと振り返り学修を含みます。 ・1年次のIPW(初期体験臨床実習): 計5日(1週) ・2年次の介護施設(早期臨床実習1): 計5日(1週) ・3年次の特別支援学校や福祉施設(早期臨床実習2): 計5日(1週) ・4年次の在宅ケア(地域社会医学実習) : 計7日 実習先と実習内容については、 ・IPW担当教員や保健学科教員が相談して、京阪神地区を中心に協力病院を募り、手を挙げて頂いた施設に受け入れをお願いしています。 ・介護施設、特別支援学校、訪問ケア実習については、本学の医学教育関係教員が自治体や業界団体を通じて協力施設を募り、ご協力頂ける施設を探しました。 ・初期臨床実習以外の教育内容については、本学教員が実習担当者を招いて実習の趣旨を述べる説明会を開いて、学生に評判の良い施設の方にプレゼンいただくなどのFD/意見交換会/説明会を毎年開いています。一方、初期体験臨床実習については、FD/説明会の類は行っていません。教育内容は実習先にお任せしていますが、チーム医療の実際がわかるような実習にしていただきたいとお願いしており、各病院の実習内容の概要を集めてパンフレットにして学生に配布しています。 ・どの実習でも、学生には実習先を選べません(自宅からの通いやすさで事務が実習先を割り振っています)。 【質問2.】 診療科指定の地域枠の遵守率はどの程度でしょうか? 特定診療科以外の科を希望した場合はどの様に対応されるのでしょうか? 【回答2.】 本学は10名の臨時定員増として地域枠を募集しておりますが、診療科指定枠ではありません。地域枠も一般枠と同じように、初期研修が終わる頃に自分が進みたい診療科を選ぶことになっています。その際、現時点で制度上認められているのは、内科、総合診療科、特定診療科(小・産・外・整・救)です。へき地には内科や総合診療が必要なので、内科と総合診療科志望者が半数以下になると種々の問題が生じることになりますが、その場合は特定診療科の人数制限をかけることも検討しています。ただ、これまでのところ制限をかけなくても、なんとかうまく回っています。 もし、小・産・外・整・救以外の診療科に進みたければ、後期研修期間(卒後6-7年目)と義務年限後(10年目以降)に研修してもらうことにしています。この場合は専門医の取得は通常より遅れることになります。 【質問3.】 地域枠医師の卒後の配置調整については神戸大学内の地域医療支援センターが関わっているとのことですが、センターが入局先の医局との調整を行うのでしょうか? 【回答3.】 神戸大学には兵庫県庁の身分をもつ特命教授が複数おり、神戸大学地域医療活性化センター(=兵庫県地域医療支援センター)を中心としてキャリア形成支援を行なっています。実際には、二人の特命教授が入局先の医局との交渉を随時行なって、養成医制度と医局人事・本人希望との調整を行なっています。県庁と神戸大学が緊密に連携できるという点で、このやり方はうまくいっています。 【質問4.】 へき地医療機関を含めた医療機関で従事する、多職種を育成するという目的が素晴らしいと感じました。 現時点で、エキスパートメディカルスタッフ育成センター、歯科医療トレーニングセンターなどを設立されておられますが、スタッフ育成センターでの具体的な活動内容、多職種がこのセンター内で一緒に学ぶ内容、研修する項目、等がありましたらご教示ください。 【回答4.】 エキスパートメディカルスタッフ育成センターや歯科医療トレーニングセンターなどは、地域枠学生・医師のためだけのものではなく、県内の地域医療に関わる医師とメディカルスタッフを対象とした地域医療人材育成事業です。神戸大学と兵庫県が一体となって、地域医療人材の卒前から卒後の教育研修を担うことにより、へき地を含めた県内の医療機関に勤務する優秀な医療者を養成することを目指しています。例えば、エキスパートメディカルスタッフ育成センターでは、県内の医療機関に従事するメディカルスタッフ(多職種)に、2-4週間フルタイムで神戸大学医学部附属病院に実習に来て頂き、高度で専門的な知識や技能を習得して頂いております。現時点のコースは、①災害・救急医療、②感染症医療、③周産期医療、④高齢者医療、⑤がん医療、⑥排泄医療、⑦栄養医療、⑧看護医療の8つのコースがあります。個々の内容は多様すぎて簡単に説明できないので、過去の活動報告書(コロナの影響をうけたR2年度と、コロナ前のH29年度)を添付いたしますのでご参照ください。 【質問5.】 兵庫県には周辺県の多くの医学部から医師派遣もあると思いますが、そのような環境が兵庫県の地域枠学生等の指導に与える影響についてご教示ください。 【回答5.】 ご指摘の通り、兵庫県とくに都市部の大病院には他府県の大学の関連病院が多く、これらの病院には研修医が集まる人気病院が多いです。しかし、これらの病院で初期・後期研修すると、その後は県外の大学に入局してしまうことが多いので、若手医師の県内定着を進める観点から難しい問題を抱えています。簡単な解決策はありませんが、この件については県庁と神戸大学は極めて密に連携しており、地域枠学生・研修医の教育体制の充実、待遇の改善、学術活動の支援などを通じて、地域の病院でも都会の大病院と比べて遜色のない研修ができるように配慮しています。また、地域枠医師に対して、上記の特定診療科(小・産・外・整・救)を認めたのも、そのようなキャリア支援の一環でもあります。また、義務年限後も、本人が希望すれば県立病院や公的病院(都会でもOK)での就職を斡旋する制度を作っています。このような複合的な支援を行なっても、都会の魅力にはなかなか勝てませんが、義務年限からの離脱防止や義務年限後の流出防止においては、少なくとも予想以上の効果は出ていると実感しています。 |
| 第6回 愛媛大学の掲載記事(R4.3.25掲載)への感想・質問 |
|---|
| ・各分野の専門医が地域で実習中の学生の指導等を行うという、素晴らしい地域医療指導体制と感じました。図1のシームレスな教育連携について、卒前、卒後、生涯教育の連携の具体例を御教示いただきたく存じます。 ・地域医療支援センターは、組織図を拝見する限り、地域枠卒業生にのみ関わるように見られますが、学内に設置されているのでしょうか。それとも県庁内になりますでしょうか。県内の他の基幹型研修病院で研修中の卒業生へも関わっているのでしょうか。卒前の地域枠学生への関与はないのでしょうか。 ・様々な機関や講座と行政の円滑な連携のために、地域医療支援センターなどで、愛媛県職員や自治医科大学卒業生などと協働する体制を構築されておられるのでしょうか。 ・とても多くの寄附講座を設置されており、関連医療機関等の地域医療への理解が深いことを感じました。これらの講座と連携して、卒前卒後教育を拡充するために、定期的なミーティング等を行われているのでしょうか。 ・「戦略型」と「提案型」の違いについて、追加説明いただけますでしょうか。 (新潟大学) |
| 【愛媛大学からの回答】 【質問1.】 各分野の専門医が地域で実習中の学生の指導等を行うという、素晴らしい地域医療指導体制と感じました。図1のシームレスな教育連携について、卒前、卒後、生涯教育の連携の具体例を御教示いただきたく存じます。 【回答1.】 総合医学教育センター長が総合臨床研修センター運営委員会委員を、総合臨床研修センター長が教務委員会委員を務めるなど、「総合医学教育センター」「総合臨床研修センター」「専門研修プログラム」のそれぞれの運営に相互に参画し合うことで情報共有ができており、シームレスな教育連携が可能となっています。例えば、OSCEやPCC OSCEには総合医学教育センター及び総合臨床研修センターが連携して関与し、専門研修プログラムへの移行に関する取り組みには総合臨床研修センターが関与しています。また、そのような連携体制の下、地域医療支援センターが地域枠学生の卒前卒後のキャリア形成に関わっています。 【質問2.】 地域医療支援センターは、組織図を拝見する限り、地域枠卒業生にのみ関わるように見られますが、学内に設置されているのでしょうか。それとも県庁内になりますでしょうか。県内の他の基幹型研修病院で研修中の卒業生へも関わっているのでしょうか。卒前の地域枠学生への関与はないのでしょうか。 【回答2.】 「地域医療支援センター」は、愛媛県の委託により愛媛大学医学部附属病院内に設置されており、医師(教員)及び事務職員はいずれも大学の職員です。 卒前の地域枠学生に対しては、「地域病院見学バスツアー」や「医学生サマーセミナー」等の企画や、説明会、面談、相談対応などを行っています。 また、他の基幹型研修病院で研修中の卒業生へも、県と合同で定期的に面談を実施し、キャリア形成支援や相談対応を行うなど、卒前から卒後まで継続して関与しています。 【質問3.】 様々な機関や講座と行政の円滑な連携のために、地域医療支援センターなどで、愛媛県職員や自治医科大学卒業生などと協働する体制を構築されておられるのでしょうか。 【回答3.】 地域医療関係者との協力関係の構築のために、「地域医療支援センター運営委員会」の委員として、地域研修病院の指導医や県医師会、行政機関の代表者等を指定しており、その中に自治医科大学OBや愛媛県職員が含まれています。委員会の審議内容に関連して、日頃から連携を密にとり地域医療に関する意見交換等を行っています。 【質問4.】 とても多くの寄附講座を設置されており、関連医療機関等の地域医療への理解が深いことを感じました。これらの講座と連携して、卒前卒後教育を拡充するために、定期的なミーティング等を行われているのでしょうか。 【回答4.】 定期的なミーティング等は行っていませんが、必要に応じて地域医療の教育等に関する事項を審議する場として、地域医療関係寄附講座教授、病院長や教務委員会委員長等で組織する委員会を設置しています。 また、コロナ感染拡大前には、年1回関係者が集まって報告会を開催しており、地域医療関係寄附講座等の取組を紹介するとともに、地域医療に関するテーマで討論を行っております。 【質問5.】 「戦略型」と「提案型」の違いについて、追加説明いただけますでしょうか。 【回答5.】 愛媛大学大学院医学系研究科が承認した将来計画等に基づいて設置する寄附講座を「戦略型」、講座等の提案に基づいて設置する寄附講座を「提案型」と区分しています。 |
| 第5回 名古屋大学の掲載記事(R4.2.25掲載)への感想・質問 |
|---|
|
Academic physician養成の取り組みを興味深く拝見しました。 |
| 【名古屋大学からの回答】 【質問1.】 地域枠学生は全員が5か月間の基礎医学セミナーで貴講座に配属される、ということですが、学生指導は、貴講座の教員がマンツーマンでされるのでしょうか(その場合、何名ほどのスタッフで)? あるいは、他の講座と連携して指導されるのでしょうか? 【回答1.】 基礎医学セミナーにおける学生指導について 当講座には私を含めて3人の教員が所属しており、この3人で講座に配属される地域枠学生を指導しております。 講座に配属される地域枠学生は例年5人ですが、留年等の関係で、年度によって3~6人と変動があります。 学生一人ずつに指導教員がマンツーマンでつきますが、量的研究の手法を学ぶ統計セミナーや質的研究の手法を学ぶワークショップ、毎週のリサーチミーティング、学生が持ち回りでおこなう抄読会(ジャーナルクラブ)、教員から抄録・スライドの作り方や発表の技法を教えるファカルティ―アワーなどは、全員参加で実施しております。 私の着任以前には、他の講座の教員と連携して指導にあたった学生の例もあったと聞いております。(研究テーマに対する学生の希望などに応じて。) 【質問2.】 卒業後、地域枠出身医師で、研究に従事したり、博士課程に入学した方がいらっしゃれば、お教えください。 【回答2.】 名古屋大学の地域枠は、現在1期生が卒後7年目を迎えております。 現在までに博士課程に入学したのは、大学5年生で一旦休学し、MD-PhDコースに入学した者1名です。当該学生は、愛知県や大学と相談を重ね、了解を得た後、試験を受けて4年間のMD-PhDコースに入りました。現在までに、数本の英文筆頭論文を発表しております。 入局している卒業生は少なくありませんが、まだ大学院に入学したという話は聞いておりません。 ただ、市中病院で初期・後期研修中に、市中病院の先生方から指導を受けて、和文・英文で症例報告や総説、原著論文を発表している卒業生も少なくありません。 |
| 第4回 香川大学の掲載記事(R4.1.27掲載)への感想・質問 |
|---|
| 【質問1.】 DXでVRを活用した地域医療実習とありますが、具体的にどのような実習を行うのでしょうか? 【質問2.】 各高校でトップにいる生徒等の学校推薦枠での選抜との意見が述べられていますが、学力試験や面接以外にどのような方法を検討されているのでしょうか?このような形での入学選抜について、社会のコンセンサスを得るためにどのような検討をされているでしょうか? (新潟大学) |
| 【香川大学からの回答】 【質問1.】 DXでVRを活用した地域医療実習とありますが、具体的にどのような実習を行うのでしょうか? 【回答1.】 国家戦略としてのデジタルトランスフォーメーションDX化は、教育の分野でも取り入れられつつあります。地域医療活動をカメラで撮影しVR(virtual
reality)動画として編集し、それをオンデマンド方式で大学間で相互利用可能なシステムを構築すれば、県内だけでなく広域の地域医療の特性を遠隔で学ぶことが可能になります。実習先は、県内に限られるのが一般的ですが、このシステムがあれば、県外の事情などを効率的に学ぶことが出来ます。また、DX化が高度に進めば、リアルタイムで遠隔の実習に参加可能になり、今後の実習の拡がりが期待されます。 現在、国・公立大学法人医学部の入試には、学校推薦指定枠は存在しません(私立大学にはあります)。学力試験や面接に加え、高校側(校長や担任教師)の責任で、将来医師たるに必要な「資質を備えた人材」を推薦できる制度設計が必要となります。 |
| 【感想】 (一部抜粋)「トップクラスの進学校からの学生でなくとも、その高校でトップでいるには成績や生活態度、課外活動など多方面で認められ、人望の篤い人材でなくてはならないことは明らかであろう。こういう人材を学校推薦枠などでとることが可能になればと思っている。」 三木医学部長の構想を是非、医学部長の在職中に実現させていただきたい。香川県は三木医学部長がおっしゃっているように面積は狭い県でR2.10.1現在で人口が約126万人の県です。東讃・中讃・西讃地区の高校には有名進学校でない高校にも該当者は必ずいると思います。 また、香川県内島しょ部のへき地と呼ばれるところには多数の高齢者がいらっしゃいます。少しでもその方たちの支援ができる医療体制の確立することをご検討いただきたい。 (匿名希望) |
|
心のこもった感想と励ましのお言葉を頂き有り難うございました。士気が強くなりました。 地域医療に身を置く医療人に求められる特性は、大病院の医師のそれとは大きく違っているように感じます。病気を治すだけではなく、地域住民の暮らしを体感して、住民の生の営みを包括的に理解できなければ地域に根ざした医療は展開できないと考えられるからです。私自身は、これから数十年先の地域医療を支える医師には、地域住民とくに、高齢者を「愛(いと)おしく想える心」が備わっていることが求められていると思っています。 このような事情が分かって、地域に貢献したいという強い想いのある高校生こそ地域枠で入学してくるべきだと考えています。医学部入試はどのような選抜であっても学力の担保はされるべきではありますが、強い志があれば少しの学力の劣勢は充分補えると考えます。どうしても医師になりたくて、3浪の末入学した学生が私の研究室で研究しています。出身は香川県内の公立高校で、医学部に入学者を出したのは30数年ぶりと聞いています。目的意識が明確で、モチベーションも高く、成績優秀です。このような学生を、目の当たりにして改めて、高校推薦枠の必要性を感じた次第です。私信を含めて回答させて頂きました。 |
| 第3回 山梨大学の掲載記事(R3.12.24掲載)への感想・質問 |
|---|
| 山梨県知事からの医療ビジョンの講義とのことですが、地域枠だけで無く他県出身の学生も対象になるのでしょうか。また、学生の反応などが分かりましたらご教示ください。 6年次の社会医学実習で県庁や保健所クリニックへ出向くとのことですが、これは全員必修になりますか?また期間はどの程度になりますか? ステークホルダーミーティングの参加者、規模(人数や頻度)、内容についてご教示ください。 シミュレータを用いた臨床医の指導はどのようなスタイルで形成されるご予定でしょうか。 (新潟大学) |
| 【山梨大学からの回答】 【質問1.】 山梨県知事からの医療ビジョンの講義とのことですが、地域枠だけで無く他県出身の学生も対象になるのでしょうか。また、学生の反応などが分かりましたらご教示ください。 【回答1.】 知事の授業は全学共通科目の「社会の中の医療・医学」の中で行われています。そのため、この授業を選択すれば全ての学部生が受講できます。ただし、医学科だけは必修科目に指定されていますので、今年度は医学科125人、その他の学部25人でした。授業アンケートは年度末ですが、マスコミのインタビューに答えていた学生は非常に良かったとのことでした。 【質問2.】 6年次の社会医学実習で県庁や保健所クリニックへ出向くとのことですが、これは全員必修になりますか?また期間はどの程度になりますか? 【回答2.】 社会医学の実習は現状では3つのグループに分かれおり、東日本大震災の被災地域、地域のクリニック、厚労省など行政機関等が派遣先となっております。したがって全員ではありません。研究テーマを与えられ、最後の報告会まで行っておりますので、実際に訪問しているのは数日間です。 【質問3.】 ステークホルダーミーティングの参加者、規模(人数や頻度)、内容についてご教示ください。 【回答3.】 学識経験者やEIP(学生教育改善プロジェクトへの参画学生)、各学部の卒業生(概ね修士課程在籍者)等が参加しています。コロナで開催が延期されてきて、まだ始まったばかりであり、今後メンバーの追加を想定しています。特に県立大学等の他大学の教育関係者には入っていただくことにしています。 【質問4.】 シミュレータを用いた臨床医の指導はどのようなスタイルで形成されるご予定でしょうか。 【回答4.】 シミュレーションセンターを利用した実習は、現状では各診療科毎に指導されています。山梨大学附属病院では、病院再開発事業を行っており、病棟Ⅲ期(来年度完成予定)においてシミュレーションセンターの拡張が予定されています。完成した後には、看護学科との合同演習を行うことを決定している等さらに活用していく予定です。また、学外の関連施設の指導医にも参加していただく構想がありますが、まだ具体的な検討までは進んでおりません。 |
| 第2回 広島大学の掲載記事(R3.11.25掲載)への感想・質問 |
|
ふるさと枠入学者1-4年生(合計72名)に対する毎週水曜日のランチョンセミナーやグループワークは、指導教員の情熱を感じるすばらしい取り組みと思います。 |
| 【広島大学からの回答】 【質問1.】 ふるさと枠入学者1-4年生(合計72名)に対する毎週水曜日のランチョンセミナーやグループワークは、指導教員の情熱を感じるすばらしい取り組みと思います。 一般枠入学者の中にも地元高校出身の学生も多いと思いますが(全体の55%が広島出身でふるさと枠は全体の15%)、これらの学生も参加できるような仕組みにしているのでしょうか? 【回答1.】 本学の取り組みにご関心を寄せて頂き、ありがとうございます。ご指摘のセミナーにつきまして、ふるさと枠学生の出席は必須としておりますが、一般入学の学生に対しては特に周知等しておらず、現在参加者はございません。もちろん断っているわけではありませんので、過去に自ら希望して参加し続けた一般学生もおりましたが、ごく少数です。 【質問2.】 今後、ふるさと枠に県外高等学校出身者を入学可能とする可能性は検討していますでしょうか? 【回答2.】 幸い今のところ、県内高校出身者のみで定員を充足できていることから、県外に門戸を広げる予定はございません。 【質問3.】 ふるさと枠の卒後9年間の義務年限のうちの4年間のうち、中山間地で勤務する時期(卒後何年目など)について指定があるでしょうか? 【回答3.】 指定はございません。なるべく早く、と各医局にお願いしておりますが、専門医取得のため中山間地勤務、特に中山間地の小病院勤務が後回しにされてしまう傾向はございます。本人のキャリアを考慮し、広島県としては医局および本人に無理強いはしておりませんが、一部の中山間地病院や自治体からはまだ医師が来ないのかと督促を受けている状況もあり、課題として認識しております。 【質問4.】 広島県は277万人の県民人口の中で、毎年270名ほどの医学科進学を果たしています。広島大学として高校生を対象とした活動をされているでしょうか? 【回答4.】 広島県が特別医学部進学者が多いとは認識しておりませんでした。高校生に医学部進学を促すような活動もないと思われます。もし多いのだとしますと、それは伝統的に私立と国立の中高一貫校が進学に強く、医学部合格者のほとんどがこれら一貫校から出ていることと何か関係があるかもしれません。進度が早く、6年かけて受験の準備をするような学校に県内の優秀層が集中しておりますので、県外の高校生に比べて多少有利に働くのかもしれません。 |
| 第1回 佐賀大学の掲載記事(R3.10.25掲載)への感想・質問 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
若年層医師の減少、勤務医・開業医の高齢化などは多くの県に通じる課題であり、「総合的な診療能力を有する医師の育成」が求められているところは首肯するところです。 |
||||||
| 【佐賀大学からの回答】 ご意見、ご質問誠にありがとうございます。
|
||||||